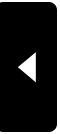♪ご訪問いただき、ありがとうございます♪
このブログは、育児を通して幸せになるママを増やすために
色々な情報をお伝えしているブログ(ご近所向け)です。
初めての方は、こちらの記事をどうぞ
★親子のふれあいを通じてもっとママが楽しく育児ができること、
★そして
★自分に自信をもって成長していける子どもを育てることを目指し、
★おうちでしっかりベビマを学ぶ、1ヶ月講座を開催しています。
★詳しくはこちらの記事からご覧ください。
(別ブログに飛びます)
このブログは、育児を通して幸せになるママを増やすために
色々な情報をお伝えしているブログ(ご近所向け)です。
初めての方は、こちらの記事をどうぞ
★親子のふれあいを通じてもっとママが楽しく育児ができること、
★そして
★自分に自信をもって成長していける子どもを育てることを目指し、
★おうちでしっかりベビマを学ぶ、1ヶ月講座を開催しています。
★詳しくはこちらの記事からご覧ください。
(別ブログに飛びます)
2009年07月16日
我が家のしりとり
我が家では、しりとりが現在ブーム。
しりとりは、昔からやってたことではあるけれど、
それが「ことわざ縛り」になってるって
どういうことですか!

3歳の娘も、
「ことわざカルタ」で覚えたことわざで
しっかり参戦。
というか、
そもそもことわざでのしりとりを始めたのは
娘本人だ…。
まさか子ども相手に
本気で考えなきゃいけなくなるのが
こんなに早いとは思わなかったよ…。
しりとりは、昔からやってたことではあるけれど、
それが「ことわざ縛り」になってるって
どういうことですか!

3歳の娘も、
「ことわざカルタ」で覚えたことわざで
しっかり参戦。
というか、
そもそもことわざでのしりとりを始めたのは
娘本人だ…。
まさか子ども相手に
本気で考えなきゃいけなくなるのが
こんなに早いとは思わなかったよ…。
2009年07月15日
これもある意味自己分析
先ほどの日記の追記です。
運動の能力は
一つだけではない、という実例を。
北畠沙代子さんという、
オリンピックのアーチェリーの選手がいらっしゃるんですが、
その方、
中学校まではバレーをやっていたそうです。
でも、レギュラーにもなれず。
高校に入って、
先輩がやっているのを見て、かっこいいとはじめたアーチェリー。
これがめきめきと、才能を発揮して、
ついにはオリンピックにまで出るほどのものになったそうです。
シドニーオリンピックでは、5位。
世界5位って、すごいことだと思います。
運動指導士さんは、彼女のことをよく知っていたそうなんですが、
バレーをやっていた頃には、
北畠さんは、才能を発揮できていなかった。
アーチェリーで必要なものは、
「止まっていられる力」
「集中力」
「極限までの精度」
などです。
(まだあるかな?詳しくなくてすみません)
北畠さんにとって、得意だったのは、
こっちだったんですね。
「運動が苦手と思う必要はないんですよ」
と、運動指導士さんは、笑いました。
走るのが遅いとか、
鉄棒ができないとか、
そういうのは、
「運動が苦手」なんじゃなくて、
「その運動に向かないだけ」の可能性があるんだそうです。
どうやっても走るのが遅くても、
運動が苦手と、思い込む必要はない。
これって、勉強とか性格でも同じことなんだよなって、
思いました。
5教科が苦手でも、
運動や音楽が、とっても得意な人がいる。
国語ができないから、
人生終わりなわけじゃない。
運動だって、それと同じ、ということで。
生きている限り、体は動かさなきゃいけないので、
自分にあった運動を見つけるってことは、
とっても大切だと、思いました。
私自身も、運動はとても苦手だと思っていたから(笑)
とっても嬉しかったです。
事実、自分がお年寄りも対象としてよく話していて、
体力がなかったり、
足が動かなかったりする方と、
なんらかの運動を続けている方の
元気さの違いに、よく驚くんです。
やっぱり、自分にあった運動って、必要かも。
私が好きな運動…、
リズムや音楽がある、動きかな?
やっぱり踊らなきゃいけませんね♪(笑)

追記
走るのが早い人は、他の運動ができると思われているけど、
例えば「縄跳びは苦手」ということがあったりするそうです。
でも、子どもの頃って、
「走るのが早い=運動能力抜群」というイメージがあるから、
縄跳びは苦手、と言い出せず、悩む子もいるんだそうで。
もしかしたら、運動能力が高い、と言われてた子は、
「自分はできるはずなんだから」と頑張って、
苦手を克服した子だったかもしれないなと、いまさらながらに思ってみました。
運動の能力は
一つだけではない、という実例を。
北畠沙代子さんという、
オリンピックのアーチェリーの選手がいらっしゃるんですが、
その方、
中学校まではバレーをやっていたそうです。
でも、レギュラーにもなれず。
高校に入って、
先輩がやっているのを見て、かっこいいとはじめたアーチェリー。
これがめきめきと、才能を発揮して、
ついにはオリンピックにまで出るほどのものになったそうです。
シドニーオリンピックでは、5位。
世界5位って、すごいことだと思います。
運動指導士さんは、彼女のことをよく知っていたそうなんですが、
バレーをやっていた頃には、
北畠さんは、才能を発揮できていなかった。
アーチェリーで必要なものは、
「止まっていられる力」
「集中力」
「極限までの精度」
などです。
(まだあるかな?詳しくなくてすみません)
北畠さんにとって、得意だったのは、
こっちだったんですね。
「運動が苦手と思う必要はないんですよ」
と、運動指導士さんは、笑いました。
走るのが遅いとか、
鉄棒ができないとか、
そういうのは、
「運動が苦手」なんじゃなくて、
「その運動に向かないだけ」の可能性があるんだそうです。
どうやっても走るのが遅くても、
運動が苦手と、思い込む必要はない。
これって、勉強とか性格でも同じことなんだよなって、
思いました。
5教科が苦手でも、
運動や音楽が、とっても得意な人がいる。
国語ができないから、
人生終わりなわけじゃない。
運動だって、それと同じ、ということで。
生きている限り、体は動かさなきゃいけないので、
自分にあった運動を見つけるってことは、
とっても大切だと、思いました。
私自身も、運動はとても苦手だと思っていたから(笑)
とっても嬉しかったです。
事実、自分がお年寄りも対象としてよく話していて、
体力がなかったり、
足が動かなかったりする方と、
なんらかの運動を続けている方の
元気さの違いに、よく驚くんです。
やっぱり、自分にあった運動って、必要かも。
私が好きな運動…、
リズムや音楽がある、動きかな?
やっぱり踊らなきゃいけませんね♪(笑)

追記
走るのが早い人は、他の運動ができると思われているけど、
例えば「縄跳びは苦手」ということがあったりするそうです。
でも、子どもの頃って、
「走るのが早い=運動能力抜群」というイメージがあるから、
縄跳びは苦手、と言い出せず、悩む子もいるんだそうで。
もしかしたら、運動能力が高い、と言われてた子は、
「自分はできるはずなんだから」と頑張って、
苦手を克服した子だったかもしれないなと、いまさらながらに思ってみました。
Posted by まこ at
16:00
│専門家にきいてみよう
2009年07月15日
運動能力は、走ることだけじゃない
「うちの子は運動が苦手」と
おっしゃっているお母様に朗報!
(というか、うちのことか…笑)
走るのが苦手でも、
球技が苦手でも、
運動が苦手とは、限らないんだそうです。
昨日は運動指導士さんと一緒にお仕事だったので、
合間に運動について、聞いてみました。
最初は「体力つける運動は、どんなものがありますか?」
という、普通のことだったんですが、
途中から、かなり興味深いお話に。
運動ができる、というのは、
走るのが速いとか、
球技がうまいとか、
鉄棒が上手とか、
そういうのをイメージしますが、
運動能力は、それだけではないとのこと。
筋力、運動能力とは
走ったり飛んだり投げたりする
瞬発力のような能力と
じっと体を保持していられるような能力、
(弓道、太極拳などがこれ)
体をうまく動かす、リズムに乗せる、
柔軟性をもたせるなどの能力
そんな、筋肉などの使い方の異なる
能力があるそうで。
走ったりするのが得意な子は、
2~3歳でもすでに
筋肉がかなりできあがっていて、
柔軟性がかなりなくなっている場合もたまにあるそうです。
うちの子は、走るのがものっすごく遅い(笑)。
まぁ、私も遅いから運動ができないのはしょうがない、と
思っていました。
でも考えてみたら、
リズムに合わせて体を動かすのは、
ものっすごく得意。
柔軟性は、まだまだかなりやわらかい。
じっとしていることは、結構できるかも。

そういうことを運動指導士さんに伝えてみたら、
「そういう人は、
エアロビクスとか、バレエとか、新体操が
向いているんですよ」
と言われました。
な~るほど!
確かに私も、走ったりするのはとっても苦手だけど、
ダンスとかなら、いつまででも踊ってられるタイプだ(笑)
今年の夏、
どうにかして体力づくりをしなければと思って、
色々考えていたんです。
でも、うちの娘さん、
小さい頃から、
体を動かすことに興味なしっ!!
走り回らないんです。
でもよ~く考えてみると、
歌って踊るんだったら、
ずっとやってるんですよね。
よし、今年の夏は、一緒にダンスだ!(笑)
ダンスダンスレボリューションが、
めちゃくちゃ欲しくなりました…。
おっしゃっているお母様に朗報!
(というか、うちのことか…笑)
走るのが苦手でも、
球技が苦手でも、
運動が苦手とは、限らないんだそうです。
昨日は運動指導士さんと一緒にお仕事だったので、
合間に運動について、聞いてみました。
最初は「体力つける運動は、どんなものがありますか?」
という、普通のことだったんですが、
途中から、かなり興味深いお話に。
運動ができる、というのは、
走るのが速いとか、
球技がうまいとか、
鉄棒が上手とか、
そういうのをイメージしますが、
運動能力は、それだけではないとのこと。
筋力、運動能力とは
走ったり飛んだり投げたりする
瞬発力のような能力と
じっと体を保持していられるような能力、
(弓道、太極拳などがこれ)
体をうまく動かす、リズムに乗せる、
柔軟性をもたせるなどの能力
そんな、筋肉などの使い方の異なる
能力があるそうで。
走ったりするのが得意な子は、
2~3歳でもすでに
筋肉がかなりできあがっていて、
柔軟性がかなりなくなっている場合もたまにあるそうです。
うちの子は、走るのがものっすごく遅い(笑)。
まぁ、私も遅いから運動ができないのはしょうがない、と
思っていました。
でも考えてみたら、
リズムに合わせて体を動かすのは、
ものっすごく得意。
柔軟性は、まだまだかなりやわらかい。
じっとしていることは、結構できるかも。

そういうことを運動指導士さんに伝えてみたら、
「そういう人は、
エアロビクスとか、バレエとか、新体操が
向いているんですよ」
と言われました。
な~るほど!
確かに私も、走ったりするのはとっても苦手だけど、
ダンスとかなら、いつまででも踊ってられるタイプだ(笑)
今年の夏、
どうにかして体力づくりをしなければと思って、
色々考えていたんです。
でも、うちの娘さん、
小さい頃から、
体を動かすことに興味なしっ!!
走り回らないんです。
でもよ~く考えてみると、
歌って踊るんだったら、
ずっとやってるんですよね。
よし、今年の夏は、一緒にダンスだ!(笑)
ダンスダンスレボリューションが、
めちゃくちゃ欲しくなりました…。
Posted by まこ at
11:10
│専門家にきいてみよう
2009年07月14日
対象年齢幅70年
今日のお仕事は、
午前と午後で、別々。
午前中は
cafe momoでベビマサークル。
午後からは、保健師として、
保健センターでお仕事。
時間がぎりぎりだったので、
移動中の車の中で、
パンを食べたりしました。

午前の対象者は
もちろん0歳児と、お母さんなんだけど、
午後からのお仕事は、
60代とか70代の方々。
これが普通の生活だから
赤ちゃんを見て
「この赤ちゃんがおばあちゃんになったときに、
『私の人生幸せよ』といえるように
なって欲しい」
と思う、私の感覚ができているんだと思います。
一緒に仕事をした運動指導士さんとかから
いいお話を聞いているんですが、
それについてはまた明日あたりに。
(時間がなくて、すみません)
午前と午後で、別々。
午前中は
cafe momoでベビマサークル。
午後からは、保健師として、
保健センターでお仕事。
時間がぎりぎりだったので、
移動中の車の中で、
パンを食べたりしました。

午前の対象者は
もちろん0歳児と、お母さんなんだけど、
午後からのお仕事は、
60代とか70代の方々。
これが普通の生活だから
赤ちゃんを見て
「この赤ちゃんがおばあちゃんになったときに、
『私の人生幸せよ』といえるように
なって欲しい」
と思う、私の感覚ができているんだと思います。
一緒に仕事をした運動指導士さんとかから
いいお話を聞いているんですが、
それについてはまた明日あたりに。
(時間がなくて、すみません)
2009年07月14日
となりのトトロでひたすら泣けるようになった
最近、娘(3歳)がトトロにはまっています。
元々私もジブリが好き。
同じくジブリ好きな相方。
二人で、ナウシカとラピュタは
セリフを丸暗記しているくらいです。

でも実はトトロ、
放映当初(小学生だったかな?)は、
それほど好きではなかったんです。
ナウシカが好きだったので、
大きな事件もおきないトトロは、ちょっとつまらなかった。
なのに今見ると、
何でかしらないけど、ひたすら泣ける。
キレイな風景に。
他愛のない会話に。
迷子になる事件に。
エンディングで、ケンカをしているさつきちゃんに。
(ちゃんと子どもらしくなれてる~…みたいな)
一つ一つが愛しくて、泣ける。
何でかな。
年取って、見方が変わったのかも。
しかし、見方を変えないのは、私の母。
テレビでトトロの放送があるたびに、
いつも電話がかかってきます。
内容はいつも同じ。
「メイちゃんは、あんたの小さい頃そっくり!!!」
…私は弟を抱えて
サツキちゃんばりの苦労人だったと思っているのに失礼な。
母の中で私は、
まだメイちゃんのままでいるんだと思うと、
なんだか微妙に複雑な気持ちです。
元々私もジブリが好き。
同じくジブリ好きな相方。
二人で、ナウシカとラピュタは
セリフを丸暗記しているくらいです。

でも実はトトロ、
放映当初(小学生だったかな?)は、
それほど好きではなかったんです。
ナウシカが好きだったので、
大きな事件もおきないトトロは、ちょっとつまらなかった。
なのに今見ると、
何でかしらないけど、ひたすら泣ける。
キレイな風景に。
他愛のない会話に。
迷子になる事件に。
エンディングで、ケンカをしているさつきちゃんに。
(ちゃんと子どもらしくなれてる~…みたいな)
一つ一つが愛しくて、泣ける。
何でかな。
年取って、見方が変わったのかも。
しかし、見方を変えないのは、私の母。
テレビでトトロの放送があるたびに、
いつも電話がかかってきます。
内容はいつも同じ。
「メイちゃんは、あんたの小さい頃そっくり!!!」
…私は弟を抱えて
サツキちゃんばりの苦労人だったと思っているのに失礼な。
母の中で私は、
まだメイちゃんのままでいるんだと思うと、
なんだか微妙に複雑な気持ちです。
2009年07月13日
ある意味英才教育?
昨日は、家族全員で、
電車の写真を撮りに走り回っていました。
なんか、珍しい電車が
走っていたそうです(よくわかってない)
写真&電車は、相方の趣味。
ほとんど興味のない私ですが、
娘は興味をもったらしい。
現在3歳ですが、
相方の一眼レフを私以上に上手に使いこなします(笑)

遠くからその風景を見て、
「あぁそっくり」と笑う私。
結構楽しいです。
電車の写真を撮りに走り回っていました。
なんか、珍しい電車が
走っていたそうです(よくわかってない)
写真&電車は、相方の趣味。
ほとんど興味のない私ですが、
娘は興味をもったらしい。
現在3歳ですが、
相方の一眼レフを私以上に上手に使いこなします(笑)

遠くからその風景を見て、
「あぁそっくり」と笑う私。
結構楽しいです。
2009年07月13日
我が家のイヤイヤ期最終話
昨日、我が家の娘のイヤイヤ期対策を
振り返ってみましたが、
私の中で「困ったイヤイヤ期」というのは、
『何をしても嫌、どうしようもなくてパニック』の状態だと思ってます。
2歳くらいの頃によくある、
自分のやりたいことをやりたくて
親がやって欲しいことに「嫌!」と言うことは
そんなにいけない事とは認識していません。
親が「こうして欲しい」と思うのを
はねつけるのは
歩けるようになって「万能感」を身につけ
「拒否」という概念をも身に着けた時期には
あって当然のことかと。
「人間」になってきているんですものね。
でも、子どもの言うことを聞いてばかりだと
生活が営めなくなる…。
だから、この時期は知恵比べでした。
子ども本人が「私が自分で選んでる!」と錯覚させ(笑)
かつ、親も困らない方法を
探ると結構だまされて(笑)面白いと思います。

例えば
「こっちとこっち、どっちがいい?」
(両方とも、親がやって欲しいこと)
…といって、
本人に「自分が選んだ気分」にさせるとか、
「お風呂入りたくないのか~。
…じゃあ、早く終わらせようか」
といってみるとか。
(この「じゃあ」がポイント。
「でも」と言ったら嫌がる子が、
意外とだまされます・笑)
あと、
小さい頃からつい、
「泣き止むまで待つ」「気持ちが落ち着くまで待つ」という
気の長~いことをしてしまっていたせいで、
(好きなタイミングでいただきますをしないと嫌がるからと、
私も夫もじっくり待ってしまって、
食事が始まるまでに20分かかったりとか…反省)
時間の概念がなかった娘に気づいてからは
好きな音楽をかけて、
「この音楽が終わるまでの間に!」と言ったら
急ぐようになりました。
この時期、押さえつけるのは
どうなのかな~と思うんですよね。
せっかくの「万能感」。
それは自信に繋がるものではないかしら。
(そりゃそれをずっと持ってたら
ちょっとうざったい中二病とかになりそうだけど・笑。
でもそのうち、自分で壁にぶつかるはずだ)
それを、
親自らが壁になって、注意ばかりをして
子どものダメさ加減を伝え続けたら
「お前なんて所詮ちっぽけなものなんだよ」
というメッセージにならないか、ちょっと心配なんです。
力比べをしたら、
親が勝つに決まってる。
子どもは「理不尽さ」で対抗してくるけれど。
(ある意味勝てないけれど)
戦うよりも、一緒に楽しむのが好きな、
私と同じように感じる方ならば、
この方法も使えるんじゃないかな~と
思います。
お役に立てそうなら
試してみてくださいね。
振り返ってみましたが、
私の中で「困ったイヤイヤ期」というのは、
『何をしても嫌、どうしようもなくてパニック』の状態だと思ってます。
2歳くらいの頃によくある、
自分のやりたいことをやりたくて
親がやって欲しいことに「嫌!」と言うことは
そんなにいけない事とは認識していません。
親が「こうして欲しい」と思うのを
はねつけるのは
歩けるようになって「万能感」を身につけ
「拒否」という概念をも身に着けた時期には
あって当然のことかと。
「人間」になってきているんですものね。
でも、子どもの言うことを聞いてばかりだと
生活が営めなくなる…。
だから、この時期は知恵比べでした。
子ども本人が「私が自分で選んでる!」と錯覚させ(笑)
かつ、親も困らない方法を
探ると結構だまされて(笑)面白いと思います。

例えば
「こっちとこっち、どっちがいい?」
(両方とも、親がやって欲しいこと)
…といって、
本人に「自分が選んだ気分」にさせるとか、
「お風呂入りたくないのか~。
…じゃあ、早く終わらせようか」
といってみるとか。
(この「じゃあ」がポイント。
「でも」と言ったら嫌がる子が、
意外とだまされます・笑)
あと、
小さい頃からつい、
「泣き止むまで待つ」「気持ちが落ち着くまで待つ」という
気の長~いことをしてしまっていたせいで、
(好きなタイミングでいただきますをしないと嫌がるからと、
私も夫もじっくり待ってしまって、
食事が始まるまでに20分かかったりとか…反省)
時間の概念がなかった娘に気づいてからは
好きな音楽をかけて、
「この音楽が終わるまでの間に!」と言ったら
急ぐようになりました。
この時期、押さえつけるのは
どうなのかな~と思うんですよね。
せっかくの「万能感」。
それは自信に繋がるものではないかしら。
(そりゃそれをずっと持ってたら
ちょっとうざったい中二病とかになりそうだけど・笑。
でもそのうち、自分で壁にぶつかるはずだ)
それを、
親自らが壁になって、注意ばかりをして
子どものダメさ加減を伝え続けたら
「お前なんて所詮ちっぽけなものなんだよ」
というメッセージにならないか、ちょっと心配なんです。
力比べをしたら、
親が勝つに決まってる。
子どもは「理不尽さ」で対抗してくるけれど。
(ある意味勝てないけれど)
戦うよりも、一緒に楽しむのが好きな、
私と同じように感じる方ならば、
この方法も使えるんじゃないかな~と
思います。
お役に立てそうなら
試してみてくださいね。
2009年07月12日
我が家のイヤイヤ期対策(2)
先ほどの日記に引き続き、
イヤイヤ期について。
さて、
「気持ちの修正がきかないんだ」ということに気づいた私。
本人も、泣きたくて泣いているわけじゃないし、
できれば一緒に、楽しくすごしたいんだろうと仮定しました。
(願望だったかもしれないけれど)
だったら、
「自分の意見を言うのはいいけれど、
泣き叫んでも、怒っても、結局は楽しくならない」
ということに気づいてもらって、
「どうやったら、やりたいことができるか」
「どうしたら楽しく過ごせるか」
って自分で考えてもらうための行動を
考えてみました。
そして、始めたのは
「何かをできたときに、一緒に喜ぶ」こと。
靴が履けたこと、
トイレにいけたこと、
歩けること、
走れること、
その当時には、もうできて数ヶ月経ってたことを
はじめてできた時のように一つ一つほめて
「やったね♪グッ♪」と声を合わせて、
親指をくっつけ合って、
喜んでみました。

できない自分に一番苛立っているのは本人だから、
できることに、目を向けてみる。
うまくいかなくて、泣きたくなったら、
「まぁそんな日もあるもんね~」と言って、
人の邪魔になりそうなときには
とっととかついで車に入れる(笑)。
でも落ち着いたら、
どうするか、話し合って、
さっき泣いた場所に戻って、もう一度やり直したり。
落ち着いた時には、
やりたいことをやるためには、
どういう風に言ったらいいか、
一緒に話し合ったりしていました。
そんなことを繰り返していたら、
わけのわからないイヤイヤは、
2週間で終わっていました。
(だからほとんどの人は、
娘のイヤイヤ期を知らないんです)
あと一つ、イヤイヤ期についてはありますが、
それはまた、明日に。
イヤイヤ期について。
さて、
「気持ちの修正がきかないんだ」ということに気づいた私。
本人も、泣きたくて泣いているわけじゃないし、
できれば一緒に、楽しくすごしたいんだろうと仮定しました。
(願望だったかもしれないけれど)
だったら、
「自分の意見を言うのはいいけれど、
泣き叫んでも、怒っても、結局は楽しくならない」
ということに気づいてもらって、
「どうやったら、やりたいことができるか」
「どうしたら楽しく過ごせるか」
って自分で考えてもらうための行動を
考えてみました。
そして、始めたのは
「何かをできたときに、一緒に喜ぶ」こと。
靴が履けたこと、
トイレにいけたこと、
歩けること、
走れること、
その当時には、もうできて数ヶ月経ってたことを
はじめてできた時のように一つ一つほめて
「やったね♪グッ♪」と声を合わせて、
親指をくっつけ合って、
喜んでみました。

できない自分に一番苛立っているのは本人だから、
できることに、目を向けてみる。
うまくいかなくて、泣きたくなったら、
「まぁそんな日もあるもんね~」と言って、
人の邪魔になりそうなときには
とっととかついで車に入れる(笑)。
でも落ち着いたら、
どうするか、話し合って、
さっき泣いた場所に戻って、もう一度やり直したり。
落ち着いた時には、
やりたいことをやるためには、
どういう風に言ったらいいか、
一緒に話し合ったりしていました。
そんなことを繰り返していたら、
わけのわからないイヤイヤは、
2週間で終わっていました。
(だからほとんどの人は、
娘のイヤイヤ期を知らないんです)
あと一つ、イヤイヤ期についてはありますが、
それはまた、明日に。
2009年07月12日
我が家でのイヤイヤ期の過ごし方(1)
日記で、娘のイヤイヤ期についてちょっと触れたら、
リアルの友達から
「あったの?イヤイヤ期!!??」っていうメールが来ました(笑)
あったんですよ、一応。イヤイヤ期。

ちょうど去年の今頃かな。
靴を履くのが嫌、
靴をお母さんが持ってきちゃったのが嫌。
お風呂に入るのが嫌。
入らないのも嫌。
あっち行って。
行かないで。
…も~、どうしたいのさっ!って感じでした。
ただ「嫌」と言うだけじゃなくて、
大声で泣くもんだから
(そして私に似たのか、声が大きいもんだから)
そのあたりがとっても大変。
「これがイヤイヤ期かぁ…」と思いつつ、
でも私も穏やかに…とか思ったけど、
通じないってのは、結構辛い!
「いや~!」という娘に
「お母さんもわかんないっ!!!」と叫んでみたりもしました。
(とりあえず、車の中にいる時限定)
そして、私がとった行動。
(1)
そういう時期なんだと認識。
とりあえず、娘の気持ちを聞いてあげて、
うまく表現できない気持ちを言ってあげるといいと聞いたので、
やってみる。
娘大泣き
↓
そうだね、靴は自分で履きたかったね。
↓
娘変わらず大泣き。
…えと、泣くのは変わらないが、
とりあえず、泣くのも気持ちを解放しているということで大事だし、
いいことにしようか。
(2)
いつ泣くのかを、観察。
本人なりの言い分(大人にとっては理不尽な理屈でも)はあるので、
それを探してみる
(3)
お腹がすいている時、眠い時等は
何をどうしてもダメだということが判明。
…そこはもう、諦める(笑)
そうでない時、
自分の思い通りにならなかった(このタイミングで話したい、など些細なこと)時
一度機嫌を損ねたら
そこから気持ちの修正をすることがとても苦手だということ、
そこがひっかかってるポイントなんだということに気付く。
ここにで気づいたら、
修正ができました。
…が、長くなりましたので、
次の日記で。
(ひっぱってごめんなさい)
リアルの友達から
「あったの?イヤイヤ期!!??」っていうメールが来ました(笑)
あったんですよ、一応。イヤイヤ期。

ちょうど去年の今頃かな。
靴を履くのが嫌、
靴をお母さんが持ってきちゃったのが嫌。
お風呂に入るのが嫌。
入らないのも嫌。
あっち行って。
行かないで。
…も~、どうしたいのさっ!って感じでした。
ただ「嫌」と言うだけじゃなくて、
大声で泣くもんだから
(そして私に似たのか、声が大きいもんだから)
そのあたりがとっても大変。
「これがイヤイヤ期かぁ…」と思いつつ、
でも私も穏やかに…とか思ったけど、
通じないってのは、結構辛い!
「いや~!」という娘に
「お母さんもわかんないっ!!!」と叫んでみたりもしました。
(とりあえず、車の中にいる時限定)
そして、私がとった行動。
(1)
そういう時期なんだと認識。
とりあえず、娘の気持ちを聞いてあげて、
うまく表現できない気持ちを言ってあげるといいと聞いたので、
やってみる。
娘大泣き
↓
そうだね、靴は自分で履きたかったね。
↓
娘変わらず大泣き。
…えと、泣くのは変わらないが、
とりあえず、泣くのも気持ちを解放しているということで大事だし、
いいことにしようか。
(2)
いつ泣くのかを、観察。
本人なりの言い分(大人にとっては理不尽な理屈でも)はあるので、
それを探してみる
(3)
お腹がすいている時、眠い時等は
何をどうしてもダメだということが判明。
…そこはもう、諦める(笑)
そうでない時、
自分の思い通りにならなかった(このタイミングで話したい、など些細なこと)時
一度機嫌を損ねたら
そこから気持ちの修正をすることがとても苦手だということ、
そこがひっかかってるポイントなんだということに気付く。
ここにで気づいたら、
修正ができました。
…が、長くなりましたので、
次の日記で。
(ひっぱってごめんなさい)
2009年07月11日
看護学生時代のお話その2
先ほどの日記の続きです。

看護学生時代のてんやわんやを
振り返ってます。
3週間目。
患者さんは、私を気に入ってくださって、
今度は手放してくれなくなりました(笑)。
一日中、病室から出られません。
看護の技術を学ぶための時間
(体を拭いたり、他の患者さんの洗髪をしたり)
離れるのが一苦労でした。
一日中、マッサージをしながらお話。
実習時間が終了したら、
大慌てでカルテ確認。
一日中、マッサージを続けていたせいで
帰りのバスは、腕が上がらなくなってました。
そして、実習最終週。
カルテの確認をして、目を見張りました。
痛み止めのモルヒネが、減っている。
つまり、痛みの訴えがものすごく減っていたんです。
そういえば、笑っていることがものすごく増えた。
少なくとも、私がいる間は痛みでうなっていることがない。
私に気を使っているかとも思いました。
でも、そうではないと、患者さんは笑いました。
もしかしたら、病状がよくなっているのかと期待しました。
それは、残念ながら、儚い期待でした。
実習最後の日。
患者さんと私、そして奥様の3人で、
泣きながらお話をして、別れました。
実習から開放されること、
激しい腕の痛みから開放されることは
なんだか、寂しいことになっていました。
実習が終わったことで、
今度は卒論と、看護師試験に全力を出すことになります。
卒論は、毎日大量の文献と戦い、
私は全学生の代表になっていました。
でも、そのことを誇らしいと思う間もなく、
ある日、家の電話が鳴りました。
あの患者さんの、奥様から。
「本当に、ありがとうございました。
あの人ね、だめでした」
静かに、奥様が伝えてくれました。
私の実習が終わった数週間後、
患者さんは、静かに息を引き取られたそうです。
「あなたが担当してくれて良かった」と
奥様は言ってくれました。
人生の最後に、とてもラッキーな出来事だったと。
あんなに笑うようになって、
あんなに穏やかに亡くなったのは、
私も信じられない、とおっしゃっていました。
その言葉は、
嬉しいと思えばいいのか、
悲しいと思えばいいのか、
実はよく、わかりませんでした。
ただただ、強い感謝のみ。
1年にわたる、長い看護実習の最後で、
あの患者さんの最期にかかわれたことは、
私にとって、本当にありがたいことだったと思います。
私は結局、看護師にはなりませんでした。
それはそれで、理由があるんですけども。
でも多分、この経験は、
一生私を支えてくれるんじゃないかと思うほどの
思い入れの強い体験です。

看護学生時代のてんやわんやを
振り返ってます。
3週間目。
患者さんは、私を気に入ってくださって、
今度は手放してくれなくなりました(笑)。
一日中、病室から出られません。
看護の技術を学ぶための時間
(体を拭いたり、他の患者さんの洗髪をしたり)
離れるのが一苦労でした。
一日中、マッサージをしながらお話。
実習時間が終了したら、
大慌てでカルテ確認。
一日中、マッサージを続けていたせいで
帰りのバスは、腕が上がらなくなってました。
そして、実習最終週。
カルテの確認をして、目を見張りました。
痛み止めのモルヒネが、減っている。
つまり、痛みの訴えがものすごく減っていたんです。
そういえば、笑っていることがものすごく増えた。
少なくとも、私がいる間は痛みでうなっていることがない。
私に気を使っているかとも思いました。
でも、そうではないと、患者さんは笑いました。
もしかしたら、病状がよくなっているのかと期待しました。
それは、残念ながら、儚い期待でした。
実習最後の日。
患者さんと私、そして奥様の3人で、
泣きながらお話をして、別れました。
実習から開放されること、
激しい腕の痛みから開放されることは
なんだか、寂しいことになっていました。
実習が終わったことで、
今度は卒論と、看護師試験に全力を出すことになります。
卒論は、毎日大量の文献と戦い、
私は全学生の代表になっていました。
でも、そのことを誇らしいと思う間もなく、
ある日、家の電話が鳴りました。
あの患者さんの、奥様から。
「本当に、ありがとうございました。
あの人ね、だめでした」
静かに、奥様が伝えてくれました。
私の実習が終わった数週間後、
患者さんは、静かに息を引き取られたそうです。
「あなたが担当してくれて良かった」と
奥様は言ってくれました。
人生の最後に、とてもラッキーな出来事だったと。
あんなに笑うようになって、
あんなに穏やかに亡くなったのは、
私も信じられない、とおっしゃっていました。
その言葉は、
嬉しいと思えばいいのか、
悲しいと思えばいいのか、
実はよく、わかりませんでした。
ただただ、強い感謝のみ。
1年にわたる、長い看護実習の最後で、
あの患者さんの最期にかかわれたことは、
私にとって、本当にありがたいことだったと思います。
私は結局、看護師にはなりませんでした。
それはそれで、理由があるんですけども。
でも多分、この経験は、
一生私を支えてくれるんじゃないかと思うほどの
思い入れの強い体験です。
2009年07月11日
看護学生時代のお話
昨日書いた、卒論のお話。
書きながら、いろんなことを思い出しました。
なので、この週末は、
私の看護学生時代のお話なんか。
卒論のテーマは、
昨日書いたとおり、「痛みとマッサージの関連性」
でした。
すごく軽い気持ちで(いや、真面目ではあったんだけど)決めたので、
それがどれほど大変なことなのか、
気づいてなかったんです。最初は。
希望通り、担当したのは、
肺がんの、末期の患者さんでした。
肺はもう、半分機能せず、
息苦しさと、
全身へ癌が転移したことによる痛み、
「もう先はない」という思いから、
痛みだけではく、
怒り、苦しみ、やるせなさを
強く抱えている患者さんでした。
奥様も、病室に入れず、
夜は自分で点滴を引き抜いて、
血まみれになりながら、
他の病棟を歩き回っているという話でした。
お年寄りにはとても気に入ってもらえることが多くて、
今までの実習で、苦労したことがなかった私。
(患者さん相手には)
最後の実習で、
私は初めての試練を迎えることになったのでした。

まず、病室に入れない。
奥様でも追い返されてるのに、
半人前の看護学生なんて、とんでもない。
マッサージどころか、そばに行けません。
なんとかそばに行っても、
触らせてもらうこともできない。
実習期間は4週間。
卒論のことを考えて、
自分でも色々計画をたてては行ったのですが、
まずは信頼関係から躓いてしまって、
最初の1週間は、
ナースステーションでカルテを調べたりすることで、
一日のほとんどが終わっていました。
2週間目も終わりの頃。
少しずつ、そばにいさせてくれることを許してくれて、
少しだけ、足のマッサージをさせてくれるようになりました。
冷たく、黒くなってしまった足。
触ることで痛みはないけれども、
それで、何が変わるわけでもない。
でも、看護学生だった私は必死でした。
いつのまにか卒論のことは、
二の次になっていました。
マッサージをしながら、コミュニケーションをとりたい。
話しかけても全然相手をしてくれなかった患者さんが、
だんだん、ぽつりぽつりと話してくれるようになりました。
若い頃のこと、
自分の病気のこと、
痛みのこと。
痛みは普通の痛み止めで止められるレベルではなく、
普段から強い鎮痛剤を使い、
痛みがひどくなってきたら、モルヒネを使うようにしていました。
それでも痛くて、うなっていることが何度も。
なんとかならないのかと、
力のない自分が、辛くてたまりませんでした。
長くなるので、わけます。
書きながら、いろんなことを思い出しました。
なので、この週末は、
私の看護学生時代のお話なんか。
卒論のテーマは、
昨日書いたとおり、「痛みとマッサージの関連性」
でした。
すごく軽い気持ちで(いや、真面目ではあったんだけど)決めたので、
それがどれほど大変なことなのか、
気づいてなかったんです。最初は。
希望通り、担当したのは、
肺がんの、末期の患者さんでした。
肺はもう、半分機能せず、
息苦しさと、
全身へ癌が転移したことによる痛み、
「もう先はない」という思いから、
痛みだけではく、
怒り、苦しみ、やるせなさを
強く抱えている患者さんでした。
奥様も、病室に入れず、
夜は自分で点滴を引き抜いて、
血まみれになりながら、
他の病棟を歩き回っているという話でした。
お年寄りにはとても気に入ってもらえることが多くて、
今までの実習で、苦労したことがなかった私。
(患者さん相手には)
最後の実習で、
私は初めての試練を迎えることになったのでした。

まず、病室に入れない。
奥様でも追い返されてるのに、
半人前の看護学生なんて、とんでもない。
マッサージどころか、そばに行けません。
なんとかそばに行っても、
触らせてもらうこともできない。
実習期間は4週間。
卒論のことを考えて、
自分でも色々計画をたてては行ったのですが、
まずは信頼関係から躓いてしまって、
最初の1週間は、
ナースステーションでカルテを調べたりすることで、
一日のほとんどが終わっていました。
2週間目も終わりの頃。
少しずつ、そばにいさせてくれることを許してくれて、
少しだけ、足のマッサージをさせてくれるようになりました。
冷たく、黒くなってしまった足。
触ることで痛みはないけれども、
それで、何が変わるわけでもない。
でも、看護学生だった私は必死でした。
いつのまにか卒論のことは、
二の次になっていました。
マッサージをしながら、コミュニケーションをとりたい。
話しかけても全然相手をしてくれなかった患者さんが、
だんだん、ぽつりぽつりと話してくれるようになりました。
若い頃のこと、
自分の病気のこと、
痛みのこと。
痛みは普通の痛み止めで止められるレベルではなく、
普段から強い鎮痛剤を使い、
痛みがひどくなってきたら、モルヒネを使うようにしていました。
それでも痛くて、うなっていることが何度も。
なんとかならないのかと、
力のない自分が、辛くてたまりませんでした。
長くなるので、わけます。
2009年07月11日
暑いから…
最近、夜がめちゃくちゃ暑いですよね。鹿児島地方。
娘が夜に起きて、「暑い…暑い…」とうめくので
困ってます。
で、途中でクーラーや扇風機を稼動させるわけですが。
最近、朝起きると、
娘が必ず
片方の肩を出しているので、毎回驚くんです。

寝ている間に無意識に。
器用だなぁ。
「○山の金さん」と
「原始人」で、
娘の呼び名の意見が分かれています。
(私と夫で)
娘が夜に起きて、「暑い…暑い…」とうめくので
困ってます。
で、途中でクーラーや扇風機を稼動させるわけですが。
最近、朝起きると、
娘が必ず
片方の肩を出しているので、毎回驚くんです。

寝ている間に無意識に。
器用だなぁ。
「○山の金さん」と
「原始人」で、
娘の呼び名の意見が分かれています。
(私と夫で)
2009年07月10日
痛みを軽くする
先ほどのお話に続いてもう一つ。
なでるということは、
実際に、痛みを弱くする作用があるんです。

実はこれ、私の卒論のテーマでもあったんです。
「『痛いの痛いの飛んでいけ』は、本当に効くのか」
(実際は、題名違いましたが)
これを思い出したとき、
自分の中で「なでること」は
長い時間、気になっているテーマだったんだと気づきました。
看護学生時代、
痛みとマッサージの間に関連性があるのかどうか、
それを調べたいと、
私は痛みのある末期がん患者さんの担当にしてもらいました。
それはそれは、いろんな葛藤があったんですが、
(これについては、後から書こうかと)
最終的に、
マッサージをすることで、
痛み止めのモルヒネの使用量が、がくんと減ったんです。
これは私がやった一例でしかないので、
それを絶対とすることはできませんが、
マッサージをする、なでさすることは、
痛みとは別の刺激をすることで、
痛みを紛らわせることになるそうです。
脳や脊髄への刺激が
「足の痛み」だけでなく
「足を触られている感じ」
「手を触られている感触」などに分散する、
というとわかりやすいでしょうか。
しかも、痛みは感情に強く左右されます。
怒りや悲しみなどを強くもっていると、
痛みは強く感じられるそうです。
(痛くて泣いていても、
飴をもらって嬉しくなったら、笑い出す子ども。
あれは、泣いていたのが嘘泣きなのではなくて、
嬉しいせいで、痛みがなくなったということです)
痛みは、傷の大きさと相関するものではありません。
痛みに強い人、弱い人がいるように、
同じ人間の、同じ傷の深さでも、
痛みを強く感じたり、あまり感じなかったりすることが
実際にあるんです。
だから、
子どもが痛がっている時は、
ぜひ、撫でてあげて欲しいと思っています。
慢性的な痛みがあったりする子は特に。
ママの手は、魔法の手です。
知り合いでしかなかった私が、
末期がん患者の痛みを少し、やわらげられたんだから、
子どもにとって、お母さんに撫でられることは
どれだけのパワーがあるんだろうと思います。
なでるということは、
実際に、痛みを弱くする作用があるんです。

実はこれ、私の卒論のテーマでもあったんです。
「『痛いの痛いの飛んでいけ』は、本当に効くのか」
(実際は、題名違いましたが)
これを思い出したとき、
自分の中で「なでること」は
長い時間、気になっているテーマだったんだと気づきました。
看護学生時代、
痛みとマッサージの間に関連性があるのかどうか、
それを調べたいと、
私は痛みのある末期がん患者さんの担当にしてもらいました。
それはそれは、いろんな葛藤があったんですが、
(これについては、後から書こうかと)
最終的に、
マッサージをすることで、
痛み止めのモルヒネの使用量が、がくんと減ったんです。
これは私がやった一例でしかないので、
それを絶対とすることはできませんが、
マッサージをする、なでさすることは、
痛みとは別の刺激をすることで、
痛みを紛らわせることになるそうです。
脳や脊髄への刺激が
「足の痛み」だけでなく
「足を触られている感じ」
「手を触られている感触」などに分散する、
というとわかりやすいでしょうか。
しかも、痛みは感情に強く左右されます。
怒りや悲しみなどを強くもっていると、
痛みは強く感じられるそうです。
(痛くて泣いていても、
飴をもらって嬉しくなったら、笑い出す子ども。
あれは、泣いていたのが嘘泣きなのではなくて、
嬉しいせいで、痛みがなくなったということです)
痛みは、傷の大きさと相関するものではありません。
痛みに強い人、弱い人がいるように、
同じ人間の、同じ傷の深さでも、
痛みを強く感じたり、あまり感じなかったりすることが
実際にあるんです。
だから、
子どもが痛がっている時は、
ぜひ、撫でてあげて欲しいと思っています。
慢性的な痛みがあったりする子は特に。
ママの手は、魔法の手です。
知り合いでしかなかった私が、
末期がん患者の痛みを少し、やわらげられたんだから、
子どもにとって、お母さんに撫でられることは
どれだけのパワーがあるんだろうと思います。
2009年07月10日
成長痛とマッサージ
先日、
4歳のお子さんの成長痛で痛がっていたところを
ベビーマッサージをしてあげたら
痛がらなくなった、というお話をお聞きしました。
「ベビマってすごいんですね!」と
興奮気味に言っていただいたんですが、
実は私のほうが驚いたり(笑)
いやぁ、すごいんですね(笑)
でも考えてみたら、
そりゃあ効くこともあるよな、という原因が
色々ありました。
ということで、今日は痛みとマッサージについて。
成長痛。
これ、医学的に本当は、名称がないんだそうです。
一般的に言われているだけ。
「子どもが成長する時、特に夜などに関節の痛みを訴える」
というものは、
医学的には原因不明とされることが実は多くて、
「骨端症(こったんしょう)」というものが
成長痛の名称とされているようです
骨端症についてはこちらがわかりやすいと思います。
http://www.k4.dion.ne.jp/~fuu/top11.htm
でも、この骨端症だけでなく、
精神的な(ストレス性の)もの、自律神経的なもの
疲労性のものから、
痛みが出ていることもあるそうなんです。
統計データ的に
神経質なタイプの子、
兄弟の上の子、
甘えが強い子
が成長痛を訴えることが多いと言われています。
(うちの子、兄弟が生まれたら
成長痛訴えそうだ…)
そして、
弟や妹が生まれたり、
母親が仕事を始めたりして、
ストレスがかかったときに起こる
ということもままあることだとか。
これは、
「親にこっちを向いて欲しい」という
無意識の思いがあって、
それが「痛み」という形に表現されるのかもしれない。
一種の心身症なのかもしれません。
親に「こっちを向いて欲しい」と思っていたことが原因だとしても、
けして「親を困らせよう」と思ってのことではないと思います。
そして、本人は本当に痛いんです。
親をだましているわけじゃないんです。
だから、マッサージが効くのかもしれません。
「一過性のものだから」
「成長すればそのうち治るから」
…と、ほったらかすのではなくて、
「痛いね」「辛いね」と
親がなでてあげることで、
親はちゃんと、自分を向いてくれるんだと
安心できる。
「足が伸びているから痛いんだね」
「痛いけどがんばってる、強い子だね」
と伝えることで
自分のイメージがよくなる。
これって、
ベビマが得意とすることです。
成長痛を訴えているお子さんがいる方、
病院に行っても、「処置はない」と言われちゃった方、
よかったら、試してみてください。
即効性はないとは思いますが、
(薬とか、専門的なマッサージではないので)
じわじわと、よくなるんじゃないかと思います。
そして、少なくとも
「あなたを見ているよ」というメッセージは
伝わるはずです。
4歳のお子さんの成長痛で痛がっていたところを
ベビーマッサージをしてあげたら
痛がらなくなった、というお話をお聞きしました。
「ベビマってすごいんですね!」と
興奮気味に言っていただいたんですが、
実は私のほうが驚いたり(笑)
いやぁ、すごいんですね(笑)
でも考えてみたら、
そりゃあ効くこともあるよな、という原因が
色々ありました。
ということで、今日は痛みとマッサージについて。
成長痛。
これ、医学的に本当は、名称がないんだそうです。
一般的に言われているだけ。
「子どもが成長する時、特に夜などに関節の痛みを訴える」
というものは、
医学的には原因不明とされることが実は多くて、
「骨端症(こったんしょう)」というものが
成長痛の名称とされているようです
骨端症についてはこちらがわかりやすいと思います。
http://www.k4.dion.ne.jp/~fuu/top11.htm
でも、この骨端症だけでなく、
精神的な(ストレス性の)もの、自律神経的なもの
疲労性のものから、
痛みが出ていることもあるそうなんです。
統計データ的に
神経質なタイプの子、
兄弟の上の子、
甘えが強い子
が成長痛を訴えることが多いと言われています。
(うちの子、兄弟が生まれたら
成長痛訴えそうだ…)
そして、
弟や妹が生まれたり、
母親が仕事を始めたりして、
ストレスがかかったときに起こる
ということもままあることだとか。
これは、
「親にこっちを向いて欲しい」という
無意識の思いがあって、
それが「痛み」という形に表現されるのかもしれない。
一種の心身症なのかもしれません。
親に「こっちを向いて欲しい」と思っていたことが原因だとしても、
けして「親を困らせよう」と思ってのことではないと思います。
そして、本人は本当に痛いんです。
親をだましているわけじゃないんです。
だから、マッサージが効くのかもしれません。
「一過性のものだから」
「成長すればそのうち治るから」
…と、ほったらかすのではなくて、
「痛いね」「辛いね」と
親がなでてあげることで、
親はちゃんと、自分を向いてくれるんだと
安心できる。
「足が伸びているから痛いんだね」
「痛いけどがんばってる、強い子だね」
と伝えることで
自分のイメージがよくなる。
これって、
ベビマが得意とすることです。
成長痛を訴えているお子さんがいる方、
病院に行っても、「処置はない」と言われちゃった方、
よかったら、試してみてください。
即効性はないとは思いますが、
(薬とか、専門的なマッサージではないので)
じわじわと、よくなるんじゃないかと思います。
そして、少なくとも
「あなたを見ているよ」というメッセージは
伝わるはずです。
2009年07月10日
充電
昨日の仕事は恐ろしく忙しくて、
しかも長時間で
家に帰ったらもう、ぐったりでした。
なかなか夕食の準備をする気合も入らなくて、
娘に泣き言。

頭をなでてもらえました。
こういう時の娘は
私の充電器(笑)
いつもありがとう。
今日のお仕事は午後だけの予定なので、
記事をアップできる…予定です。
しかも長時間で
家に帰ったらもう、ぐったりでした。
なかなか夕食の準備をする気合も入らなくて、
娘に泣き言。

頭をなでてもらえました。
こういう時の娘は
私の充電器(笑)
いつもありがとう。
今日のお仕事は午後だけの予定なので、
記事をアップできる…予定です。
2009年07月08日
ばて気味…
なんだかちょっと、ばて気味です。

風邪のひきかけかな。
それとももはや夏ばて?
鹿児島は確かに最近めちゃくちゃ暑いけど、
(暑くて夜、目が覚める)
まだばてるには早いだろう~!!!
でも、体が休息を求めているのは確かっぽかったので、
今日は20分ほどお昼寝までしちゃいました。
明日は一日中、目いっぱいお仕事なんです。
っていうか、これから2週間、
仕事の予定がみっちりなんです。
ばててる暇はなぁい!
幸い、今日は義理の実家と一緒に
うなぎなんか食べにいけちゃって♪
栄養はたっぷり補充できました。
後は睡眠さえとってしまえばきっと大丈夫!
明日またがんばるぞ~!おう!!

風邪のひきかけかな。
それとももはや夏ばて?
鹿児島は確かに最近めちゃくちゃ暑いけど、
(暑くて夜、目が覚める)
まだばてるには早いだろう~!!!
でも、体が休息を求めているのは確かっぽかったので、
今日は20分ほどお昼寝までしちゃいました。
明日は一日中、目いっぱいお仕事なんです。
っていうか、これから2週間、
仕事の予定がみっちりなんです。
ばててる暇はなぁい!
幸い、今日は義理の実家と一緒に
うなぎなんか食べにいけちゃって♪
栄養はたっぷり補充できました。
後は睡眠さえとってしまえばきっと大丈夫!
明日またがんばるぞ~!おう!!
2009年07月08日
9つの性格
自己分析シリーズ(笑)
今日は、「9つの性格」です。
9つの性格



結構有名な本らしいですね。
(だいぶ昔に発行されてますが)
「エニアグラム」
というもののことで、
人の性格は、実は9つのパターンに分類できる、というものです。
アメリカなどでは結構研究されていて、
GMとか大きな企業などでも、採用されているそうですよ。
(こういう性格診断を企業が採用するってのは
結構すごいなぁ)

9つのタイプは、
(1)完全でありたい人、
(2)人の助けになりたい人、
(3)成功を追い求める人、
(4)特別な存在であろうとする人、
(5)知識を得て観察する人、
(6)安全を求め慎重に行動する人、
(7)楽しさを求め行動する人、
(8)強さを求め自己主張する人、
(9)調和と平和を願う人
だそうです。
診断のサイトも、探してみました。
《SQ》
http://sq-life.jp/enneagram/(こちらはわりと簡単)
《究極のエニアグラム》
http://www.mirai.ne.jp/~ryutou-m/index2.htm
こちらの「性格自己分析室」にも。
内容ものすごく詳しいです。
私は、本でやったときも、上のサイトでやったときも
「2」の助けになりたい人、でした。
人の助けになりたい、
子ども好き、社交的、
親切心が強い、おもいやりがある
…なんて言われると、嬉しくなりますが、
・人を信じやすく、だまされやすい
うっ。
・人に必要とされたがる。
…ご、ごもっとも。
・慕われたがり、善い人間に思われたがる。
そのとおり。
そして、
・人に必要とされることで、自分の存在価値を見ようとする。
そのとおりですごめんなさい~(なぜか謝る)
人の評価に左右されがちなタイプで、
相手が望んでいると思われるような行動をとろうとするので、
どんな人なのかわかりにくいし、
自分でもわからなくなるタイプらしい。
自分の軸がないというのは、
本当にそのまんまで、
なんていうかもう、参りました、って感じでした。
ただ、このエニアグラムのすごいところは、
「自分がとらわれやすい」所を知ることができることや、
「こういう風に成長すると、バランスが取れる」というものがあること。
タイプ2は、
「自分は特別である」という意識を持つことができると
楽になるということを書いてあって、
なんだか納得したりもしました。
あと、
それぞれに意識が向きやすい方向、
(「7つの基本理論」の中の5番目の記事に書いてあります)
タイプ2は、「子ども」だとの事。
「子どもに向く」とは自分の実子だけでなく子ども集団や教育問題、
子どもをとりまく環境など、すべて子どもに関することに意識上で
も無意識下でも向いていることを指します。
タイプ2はそっ先して善いことを行えばより善い社会になると思い
込んでいます。それゆえ、子どもたちを次代を担う立派な善い人間に
育て上げる義務と責任があると思っています。教育に熱心となり、子
どもの養育全般に、広く深く関わる傾向があります。また、他人から
子どもが攻撃されると怒りは大きく、自分の力以上のものを出して、
交戦して行きます。
なお、タイプ2は危険をかえりみず自己犠牲もいとわず、人々を
窮地から救い出したときほど充実感を得られることはないでしょう。
…私そのまんまやないけ~!!(興奮)
個人的に、とっても面白かったです。
基本的に「お母さん」のタイプで、
そそっかしい、という言葉があったことも
なんか微妙な気分になりました。
私がそそっかしいのはそのせいか~♪なるほどなるほど。
…って、納得しちゃだめか。
今日は、「9つの性格」です。
9つの性格

結構有名な本らしいですね。
(だいぶ昔に発行されてますが)
「エニアグラム」
というもののことで、
人の性格は、実は9つのパターンに分類できる、というものです。
アメリカなどでは結構研究されていて、
GMとか大きな企業などでも、採用されているそうですよ。
(こういう性格診断を企業が採用するってのは
結構すごいなぁ)

9つのタイプは、
(1)完全でありたい人、
(2)人の助けになりたい人、
(3)成功を追い求める人、
(4)特別な存在であろうとする人、
(5)知識を得て観察する人、
(6)安全を求め慎重に行動する人、
(7)楽しさを求め行動する人、
(8)強さを求め自己主張する人、
(9)調和と平和を願う人
だそうです。
診断のサイトも、探してみました。
《SQ》
http://sq-life.jp/enneagram/(こちらはわりと簡単)
《究極のエニアグラム》
http://www.mirai.ne.jp/~ryutou-m/index2.htm
こちらの「性格自己分析室」にも。
内容ものすごく詳しいです。
私は、本でやったときも、上のサイトでやったときも
「2」の助けになりたい人、でした。
人の助けになりたい、
子ども好き、社交的、
親切心が強い、おもいやりがある
…なんて言われると、嬉しくなりますが、
・人を信じやすく、だまされやすい
うっ。
・人に必要とされたがる。
…ご、ごもっとも。
・慕われたがり、善い人間に思われたがる。
そのとおり。
そして、
・人に必要とされることで、自分の存在価値を見ようとする。
そのとおりですごめんなさい~(なぜか謝る)
人の評価に左右されがちなタイプで、
相手が望んでいると思われるような行動をとろうとするので、
どんな人なのかわかりにくいし、
自分でもわからなくなるタイプらしい。
自分の軸がないというのは、
本当にそのまんまで、
なんていうかもう、参りました、って感じでした。
ただ、このエニアグラムのすごいところは、
「自分がとらわれやすい」所を知ることができることや、
「こういう風に成長すると、バランスが取れる」というものがあること。
タイプ2は、
「自分は特別である」という意識を持つことができると
楽になるということを書いてあって、
なんだか納得したりもしました。
あと、
それぞれに意識が向きやすい方向、
(「7つの基本理論」の中の5番目の記事に書いてあります)
タイプ2は、「子ども」だとの事。
「子どもに向く」とは自分の実子だけでなく子ども集団や教育問題、
子どもをとりまく環境など、すべて子どもに関することに意識上で
も無意識下でも向いていることを指します。
タイプ2はそっ先して善いことを行えばより善い社会になると思い
込んでいます。それゆえ、子どもたちを次代を担う立派な善い人間に
育て上げる義務と責任があると思っています。教育に熱心となり、子
どもの養育全般に、広く深く関わる傾向があります。また、他人から
子どもが攻撃されると怒りは大きく、自分の力以上のものを出して、
交戦して行きます。
なお、タイプ2は危険をかえりみず自己犠牲もいとわず、人々を
窮地から救い出したときほど充実感を得られることはないでしょう。
…私そのまんまやないけ~!!(興奮)
個人的に、とっても面白かったです。
基本的に「お母さん」のタイプで、
そそっかしい、という言葉があったことも
なんか微妙な気分になりました。
私がそそっかしいのはそのせいか~♪なるほどなるほど。
…って、納得しちゃだめか。
2009年07月07日
子どもの成長に悩んだら
先日のベビマサークルで、
相談がありました。
「うちの子、2ヶ月なのにすごく寝るんです。
オムツがぬれても泣かないんです。
大丈夫でしょうか」
夜寝ることで、おっぱいが張りすぎるとか、
問題がありますか? --NO
何か痛いことがあったりしたら
ちゃんと泣きますか? --YES
その他いくつかの質問をさせていただいて、
「手のかからない子なんですね。
ラッキーでしたね」
という結論に至りました(笑)

赤ちゃんが生まれてからしばらく、
特に第一子の頃って、
不安いっぱいなんですよね。
寝てくれない、体重が増えない、
泣いてばかり、離乳食を食べない
というものだけでなくて、
すごく寝る
すごく食べる、
すごく元気に動く
ということも心配の種になるんだなと、
最近しみじみ思います。
本当に、赤ちゃんって、
育児書どおりに育たない!
育児書の「この時期はこう育つ」というのは
あくまでも参考にしておいたほうがいい、というのは定説ですが、
本当に、びっくりするくらいの個人差ですよ。
そう言っている自分も、
娘の最初に生えた歯が、順番が違っていて
(普通は下か上の、真ん中から生えることが多い。
でも、その横が最初に生えたの)
「大丈夫か!?」と
思ったりしたものですが(恥)
最初の一年の心配は
病気とかでなければ、ほとんどの場合、
3年後には笑い話になっている物。
よく動く子は、
将来、運動能力が有望なのかも。
すごく泣くタイプの子は、
すごく感性が強いのかも。
(自分の子はそのタイプだったんじゃないかと思う)
細い子は(元気なら)
大きくなったら、細くてうらやましがられる子になるのかも。
寝てくれない子は、
少ない睡眠で活動できる、ショートスリーパーなのかも。
(すごく寝ないとダメな私にはうらやましい)
まぁ、小さい頃は寝てくれないのに、
大きくなったら起きてくれないとかも
ままある話ではありますが(苦笑)。
病気かどうか、発達が大丈夫かというものをチェックするために
健診があって、
色々チェックしてもらうわけですから、
そこで問題なければ、
どーんと構えちゃってもいいと思います。
あ、でも心配になる方。
それはそれで、何かを早く気づけるかもしれない。
それはそれで素敵なことなので、
「心配しちゃいけない…でも気になる」というストレスが
少なくなるといいですね。
相談がありました。
「うちの子、2ヶ月なのにすごく寝るんです。
オムツがぬれても泣かないんです。
大丈夫でしょうか」
夜寝ることで、おっぱいが張りすぎるとか、
問題がありますか? --NO
何か痛いことがあったりしたら
ちゃんと泣きますか? --YES
その他いくつかの質問をさせていただいて、
「手のかからない子なんですね。
ラッキーでしたね」
という結論に至りました(笑)

赤ちゃんが生まれてからしばらく、
特に第一子の頃って、
不安いっぱいなんですよね。
寝てくれない、体重が増えない、
泣いてばかり、離乳食を食べない
というものだけでなくて、
すごく寝る
すごく食べる、
すごく元気に動く
ということも心配の種になるんだなと、
最近しみじみ思います。
本当に、赤ちゃんって、
育児書どおりに育たない!
育児書の「この時期はこう育つ」というのは
あくまでも参考にしておいたほうがいい、というのは定説ですが、
本当に、びっくりするくらいの個人差ですよ。
そう言っている自分も、
娘の最初に生えた歯が、順番が違っていて
(普通は下か上の、真ん中から生えることが多い。
でも、その横が最初に生えたの)
「大丈夫か!?」と
思ったりしたものですが(恥)
最初の一年の心配は
病気とかでなければ、ほとんどの場合、
3年後には笑い話になっている物。
よく動く子は、
将来、運動能力が有望なのかも。
すごく泣くタイプの子は、
すごく感性が強いのかも。
(自分の子はそのタイプだったんじゃないかと思う)
細い子は(元気なら)
大きくなったら、細くてうらやましがられる子になるのかも。
寝てくれない子は、
少ない睡眠で活動できる、ショートスリーパーなのかも。
(すごく寝ないとダメな私にはうらやましい)
まぁ、小さい頃は寝てくれないのに、
大きくなったら起きてくれないとかも
ままある話ではありますが(苦笑)。
病気かどうか、発達が大丈夫かというものをチェックするために
健診があって、
色々チェックしてもらうわけですから、
そこで問題なければ、
どーんと構えちゃってもいいと思います。
あ、でも心配になる方。
それはそれで、何かを早く気づけるかもしれない。
それはそれで素敵なことなので、
「心配しちゃいけない…でも気になる」というストレスが
少なくなるといいですね。
2009年07月06日
今日の結果
今日はなんとか、
二部屋ほど、模様替えができました。

たんすとかの大物、
意外と力持ちなので、平気で運びますが、
これを誰かが見たら、あわてるかもな、と
一人ほくそえんでました(苦笑)
(身長が146センチしかないもので、
荷物を運ぶと
その対象がものすごく大きく見えるのです)
今回の模様替えは、
「物を、あるべき場所に移動する」という目的のもの。
今まで、あんまり物を考えずに置いているせいで、
動線は悪いし
部屋は片付かないし。
(これは私が片付けないのが悪いのか)
何よりも、わが家
『子どもがいる家仕様』になっていないのです。
娘が小さい頃から
「これは危ないから触らないでね」と言えば
絶対に触らない人だから。
だから、ガスもパソコンもなにもかも、
子どもを阻む形になっていない。
でも、
二人目が生まれて、
こんなに楽とは限らない。
(というより、まず無理だろう)
ということで、
色々考えつつ、活動中です。
まだ一番問題の、キッチンが残ってる…。
頑張ります。
そして、
最近お役立ち情報をお伝えできてなくてすみません。
見捨てずに見ていてくださる皆様、
もう本当に、大好きです。
明日あたりには
何かアップしたいと思っています。
二部屋ほど、模様替えができました。

たんすとかの大物、
意外と力持ちなので、平気で運びますが、
これを誰かが見たら、あわてるかもな、と
一人ほくそえんでました(苦笑)
(身長が146センチしかないもので、
荷物を運ぶと
その対象がものすごく大きく見えるのです)
今回の模様替えは、
「物を、あるべき場所に移動する」という目的のもの。
今まで、あんまり物を考えずに置いているせいで、
動線は悪いし
部屋は片付かないし。
(これは私が片付けないのが悪いのか)
何よりも、わが家
『子どもがいる家仕様』になっていないのです。
娘が小さい頃から
「これは危ないから触らないでね」と言えば
絶対に触らない人だから。
だから、ガスもパソコンもなにもかも、
子どもを阻む形になっていない。
でも、
二人目が生まれて、
こんなに楽とは限らない。
(というより、まず無理だろう)
ということで、
色々考えつつ、活動中です。
まだ一番問題の、キッチンが残ってる…。
頑張ります。
そして、
最近お役立ち情報をお伝えできてなくてすみません。
見捨てずに見ていてくださる皆様、
もう本当に、大好きです。
明日あたりには
何かアップしたいと思っています。
2009年07月06日
今日は模様替え!
昨日の日記のとおり、
ベビマサークルの予定が、なくなった本日。
今日は、模様変えをします!

本当は、7月の目標だったの。
でも、なんだかどんどん仕事が入っちゃって、
日にちがほとんどなくなっちゃったの。
…気合を入れないと、間に合わない(夏休みも来るし)
ということで、今日は一日
大きな荷物と格闘して、頑張ります!
ベビマサークルの予定が、なくなった本日。
今日は、模様変えをします!

本当は、7月の目標だったの。
でも、なんだかどんどん仕事が入っちゃって、
日にちがほとんどなくなっちゃったの。
…気合を入れないと、間に合わない(夏休みも来るし)
ということで、今日は一日
大きな荷物と格闘して、頑張ります!