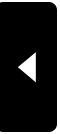このブログは、育児を通して幸せになるママを増やすために
色々な情報をお伝えしているブログ(ご近所向け)です。
初めての方は、こちらの記事をどうぞ
★親子のふれあいを通じてもっとママが楽しく育児ができること、
★そして
★自分に自信をもって成長していける子どもを育てることを目指し、
★おうちでしっかりベビマを学ぶ、1ヶ月講座を開催しています。
★詳しくはこちらの記事からご覧ください。
(別ブログに飛びます)
2010年08月16日
心を受容すると、泣き止むんですね
なかなかハッピーママの更新ができなくてすみませんでした~。
久しぶりのハッピーママ、
何を書こうかな~と思っていたんですが、
先ほどあった気付き、という
自分のことで。
ちょっとした坂道を
ムスメと一緒に手をつないで歩いていたんですが、
下り坂で、思いっきりすっころぶムスメ…。
とりあえず支えて、
「危ないから気をつけようね」
と言いつつ、
ちょっと余所見をした瞬間に、
もう一度すっころぶ…。
今度は支えられなかったばかりか、
私の足の下に手を入れてしまった(というか、突っ込んだ形に)
ために、
軽くとはいえ
指まで踏まれてしまったムスメはもう、
まさに踏んだり蹴ったり状態でした。
「痛い」と、グズグズ泣くし、
「お母さんが踏んだ」と言い続けるし、
一瞬辟易。
「だからしっかり前見て歩かなきゃ」
「お母さんはちゃんとしてたじゃない」
「わざとじゃないんだから」
そんな言葉をちょっと言ってみてしまったんですが、
そんな言葉じゃ、もちろん変化はないんですよね。
こういう場合に必要な言葉かけは、
「受容すること」と言われています。
辛かったことを、受け入れる。
本当は、子どもの方が悪かったとしても、
その「気持ち」は受け入れてあげる。
そうは言われても、とっさにはできなかったんですが、
ふと思い出して、
「うん。痛かったよね。足も手も」
「転んじゃったもんね。まだ痛い?」
そんな言葉かけをしたとたん、
けろりと泣き止んで、笑い出したムスメに私が驚きました。
うーむ、
「心を受け止める」ことのすごさに、私が驚き。
自分がまだまだ未熟なことにも気付かされましたが、
今後も精進してみたいと思いました。
試しに、やってみませんか?
今日の提案
グズグズ文句を言う、子ども。
泣いてばかりの、子ども。
大人から見たら、「そんなことで泣いて」「あんたが悪いんでしょ」
と言いたい事があるようなことでも、
そんな言葉は、泣き止ませることはできないかもしれません。
子どもの善悪はちょっと脇に置いといて、
「(あなたは)悲しかったんだね」というように、
受け入れてみませんか?
思った以上の効果があるかもしれませんよ。
2010年08月16日
子どもを褒める話、最後に
ものすごく長くなりました、「褒め」の話。
これを書くために、
本も文献も、ものすごい数読んだからな~。
インプットが多いと、
アウトプットも増える傾向に…。
子どもを褒めるとつけあがる?
ええと、
総括いきます。
褒めることでも叱ることでも、
子ども自身の可能性を伸ばしたり、
問題となりそうなことを修正したり、
というためにやることだと思います。
そこに必要なのは、
子どもを尊敬すること、
だと思っています。
尊敬、というと、違和感があるかもしれないけど、
(もうちょっといい表現ないのかなと探しているんですけども)
尊重、とも違うように思うんですよね。
子どもを下に見るんじゃなくて、
子ども自身を「輝く存在」みたいな感じで、
大切にすること。
(う~む、やっぱり「尊敬」だろうか)
駄目だと言われていることをしようが、
きちんとできていなかろうが、
子どもも一人の人格。
駄目な人なんじゃなくて、
新しい段階に行く途中の人、なんだと思います。
それを言うなら
私たち自身もまだ、
「途中の人」ですよね。
途中の人が、さらに後ろの途中の人に
「こうしたらいいんじゃないかな」と伝えている、というのが
しつけじゃないでしょうか。
私達も「途中の人」ゆえに
それが正しいかどうかはまだ、わからなかったり。
それでいいと思うんです。
でも、
人の心理的に、
肯定されると嬉しいし、
否定されると悲しいし、
無視されるともっと悲しい、
というのがある以上、
うまいこと「褒め」を使うのがいいんじゃないかと思うんです。
「褒める」のも「叱る」のもしないで
「勇気付けるんだ」という考え方にアドラー心理学がありますが、
私はその考え方、好きなんです。
「勇気付け」という言葉が、私の中でまだ完全になってないので、
うまいこと伝えられないんですが、
私が人生の中で
とっても大切だと思っている
「自己重要感」を身に着けるためにも、
「褒めること」や「叱ること」を
「子どもを(親の都合の)いい子に育てる」
ためだけの方法にするんじゃなくて、
その人自身が、
自分で歩いていけるようにちょっと後押ししてみる、
というような感じかしら。
人に褒めてもらうこと、
人に関心を寄せてもらうこと、
それは、
やっぱり子どもにとって(大人にとっても)
行動を引き出すし、
元気にするし、
伸びていく要因になると思います。
だから、
「あなたを見ているよ」
「あなたが大好きだよ」
「あなたはこんなところが素敵だよ」
というようなことを、
伝えていけばいいんじゃないかと思ったりしています。
その「褒め」のやり方は
人によってそれぞれだと思うけれど、
褒め殺しのように、褒め言葉のシャワーを浴びせるもよし、
ちょっとしたときに、ポツリと褒めるもよし、
「ここがあなたのいいところね」なんて言わなくても、
「あら?また大きくなったんじゃない?」
「今日はよく外で遊んだから、日焼けしたね」
なんて
「あなたを見ているよ」のメッセージを伝えるのも、
使えると思ったりしています。
褒めることで居心地が悪くなるんだったら、
まだ練習(?慣れ、かな)が足りないか、
やり方がちょっと、違うだけ。
あなたなりの方法で、
大切な人への気持ち、
伝えてもらいたいと思っています。
2010年08月16日
【告知】鹿児島あちこちでベビマをしにいきます
(うまくまとめられたら…)
で、その前に。
前回の告知の後、質問メールがきたので、
8月後半、
怒涛の(?)ベビマ週間のことを
もう一度告知させてくだっさい。
【蒲生町のzenzaiでベビマをします】
蒲生町の築100年以上の建物でのベビマ、
なんだかゆったりしますよ~♪
こちらのお店にも
実は生後4ヶ月(あれ?もう5ヶ月になったかな?)の
お子さんがいるんですよ~♪
■ 日時:8月27日(金) 10:30~11:30
■ 場所: 蒲生茶廊 zenzai
(蒲生町上久徳2425)
■ 料金:800円(オイル5cc込み)
■ 持ってくるもの
バスタオル1枚、小さめのタオル1枚
着替え、オムツ
赤ちゃん用の麦茶など(水分補給用)
■ 申し込み・問い合わせはtel 0995-52-1164(zenzai)まで
駐車場はあるんですが、
数が少ないですので、
できるだけ、乗り合わせもしくは徒歩でおいでくださいませ。
【わくわく子どもフェスタ】
年に一回のお楽しみ、
隼人町のわくわく子どもフェスタで今年もベビマをします。
■ 日時:8月22日(日)第一回 9:50~10:10
第二回 10:50~11:10
■ 場所:サンあもり体育館
(鹿児島県霧島市隼人町見次1371番地)
■ 料金:500円 オイル代別
■ 持ってくるもの
バスタオル1枚、小さめのタオル1枚
着替え、オムツ
赤ちゃん用の麦茶など(水分補給用)
わくわく子どもフェスタ、
未就学児までのお子さんを対象にしているんですが、かなり面白そうですよ。
●お魚つりゲーム
●ビン倒しゲーム
●新聞紙のプール
●ダンボール積み木
●ジャバラトンネル…などの、体を使った遊びコーナー。
●色々製作をするコーナー、
●飲食コーナー、
●フリーマーケットコーナーなどがあります。
また、時間によっては、
おはなしタイム、親子体操タイム、アンパンマン着ぐるみ撮影会なども。
時間は、9:30~12:30までですので、お早めにどうぞ。
(去年も、終了時間の頃にいらっしゃる方がいましたので…かわいそうで)
うちのムスメも楽しみにしているイベントです。
ぜひお出かけくださいませ~。
【いつものカフェモモベビマの日程はこちら】
■ 日 時:8月24日(火)
8月31日(火)
(17日はお休みです)
■ 時間 10:30~11:30
■ 場 所:cafe momo
■ 定 員:7~8組・先着・定員になり次第
■ 持ってくるもの
バスタオル1枚、小さめのタオル1枚
着替え、オムツ
赤ちゃん用の麦茶など(水分補給用)
■ 料金
初回→オイル購入なし800円
オイル・手順シート込み 2000円
二回目以降→以前オイルと手順シートを購入された方600円
オイルを購入されてない方800円
※ オイルはオーガニックホホバオイル50ml
手順シートはサークルの内容が復習できる、
オリジナルのものです(ラミネート済み)
■お問い合わせ、申し込みは
cafe momo 0995-43-8126 まで
※ cafe momoのブログ:http://cafemomo.chesuto.jp/
2010年08月15日
子どもを褒めるとつけあがる?
も、もう終わりかな。多分。
子どもを褒めましょう、という話をすると、
特に年配の方に(笑)よく言われることがあったりします。
「子どもはガツンと言ってしつけないと、
つけあがるよ」という言葉。
これも、一理あると思います。
何をしても、
どんな悪いことをしても、
「あらあら~♪」なんて笑って見ていたら、
多分子どもは、好き勝手なことをすると思います。
だって、子どもだから(笑)。
相手の迷惑とか、
後の状況とか、
人からの評価とか、
そういうのを考えないのが子どもです。
(まぁ年齢による成長度合いもあるだろうけど)
例えば、周りの目を気にして、やりたいことを全くしない1歳児とかがいたら
逆に私は心配です。
でも、ですね。
ある程度大きくなって、自分の行動が客観視できるくらいに成長したとき、
子どもの行動を制御できるものは、何でしょうか?
部屋の中で走り回る子、
わがままを言う子、
いろんな問題行動をとる子、
それを止めるのは、
瞬発的には「親からの叱責」が有効だろうけど、
多分、親(=怒る人)がいなくなれば
また同じになるのは簡単に予想がつきます。
それを本当に止められるのは?
何より子ども本人の意思、
そして、
その意思を引き出すための自信でしかないと思うんです。
子どもは(というか、大人もだけど)
「こいつは本当に駄目だから」
「いつも騒がしくって仕方のないやつだから」
「相手の気持ちも考えられなくって…」
等々、
そんな目で見られて、そんな風に言われていたら、
「そういう風に育つ」
と言われています。
だって、それが「その人らしい」状態だと
回りも本人も思ってますから。
「駄目で」「騒がしくって」「相手の気持ちも考えない」
のが当たり前で、
その殻を破る必要がないんですよね。
自分なんて駄目駄目だから、
悪いことをしても当たり前~と思えば、悪いことをします。
もっといくと、
悪いことでもしなければ、人が自分を見てくれないとなると、
さらにエスカレートします。
(この辺はまた、別の話ですが)
それに歯止めをかけるのが、
褒められる、承認されることでできた、
「自分は自分のままで素敵」
というような自信だったり、
「自分も、一人の人間なんだから
しっかりしなきゃ」というようなことだったりするんだと思います。
エネルギーに満ち満ちていて、
じっとしていられないような子がいます。
その子に、「お前は乱暴だから」などというような叱責だけで育てて
そのエネルギーをなくすことに尽力すると、
もったいないと思います。
そのすごいエネルギーそのものを
「これはすごいものなんだ」と承認して、
じっとできないことが問題になるんだったら
周りのことも伝えて、自分なりにどうしたらいいのか考えさせたり、
それを上手に使えるように促してあげることはできるんじゃないでしょうか。
もしかしたら、
ものすごいスポーツ選手になるかもしれない。
(そうじゃなかったとしても、
大きな自信になるし、問題行動もなくなるはず)
おとなしくって、
周りのことをよく見ているような子がいます。
その子に
「あなたはグズだから」
「引っ込み思案でだめねぇ」なんて評価だけで育てても
逆に自信がなくなるだけで
積極的になることはまずないと思います。
その子自身をよくみたら、
行動の一つ一つがとっても丁寧だったり、
すごく聞き上手だったりすることも多いんです。
その素敵なところはきちんと伝えて
おとなしいことが問題になる場合だけ、いい方法を使えるようになれば、
それもまた、すばらしいことなんじゃないでしょうか。
みんながみんな、
リーダーになる必要なんかないわけですし。
(みんながリーダーだと、まとまるものもまとまらない)
ということで、私は
「子どもが我に返らせるため、というような
瞬発的なものとしては、『ガツンと言うこと』は必要。
でも、長期的、継続的なものとしては、
褒めや承認のほうが有効」
という考えです。
多分、褒め方の話
明日に総括して、おしまいのつもりです。
2010年08月15日
褒めることの弊害
ということで、
お伝えしてきたんですが、
一つだけ、書いておいたほうがいいと思うことを
忘れてました。
それは、
褒めることの弊害。
褒めるのが苦手、とか
子どもは褒めずに育てるべき、という方は、
「弊害がある」ということを
やっぱり思われるかもしれませんね。
このあたりのことも、書いておく必要があると思っています。
褒めることが困ることになる、というのは
状況によってはやっぱりいくつかあると思います。
やっぱり一番は、
褒めることが、「評価」になってしまう場合。
前にも書きましたが、
上から目線で「えらいね」などというようなことで伝えていくと、
褒めることそのものが、「評価」「褒賞」になってしまいます。
(叱ることも、「悪い評価」「逆の褒賞」)
これで、子どもをコントロールしているんです。
ということは、
「褒められないならやらない」
ということになってしまう、ということ。
これでは本末転倒です。
そして、
私自身もそういう部分があったりしてたんですが、
人の評価が自分の評価の全てだということになると
ものすごく自信がなくなります。
周りの目を気にして、
自分のしたいことはできないし、
自分の物差しで善悪の判断ができなくなるんです。
人は、人との関係を作りながら生きていくものですが、
限度を過ぎると、
その人なりの良さが、なくなってしまうと思います。
私が考える本当の「褒め」は
その人そのものの、自信をつけること。
そのままのその人(その子)のいいところを指摘して、
時には本人が気付いてもないようなことを伝えて、
私って、私のままで素敵なんだ、
と思わせることが大事なんじゃないかと思ったりしています。
あともう一つ、
「褒めると子どもがつけあがる」ということについて、
もう一つの記事で書いておきたいと思います。
2010年08月14日
お盆ですね
とりあえず、実家にきております。
(とりあえず、というのは、
一応父のお仏壇などはあるものの、お墓がまだできておらず、
迎えも送りもないためだったりします)
隙間をみつけて、更新するつもりだったんですが、
隙間を見つけられませんでした(汗)
すみません~。
ハッピーママ、今日はお休みしますね。
ではでは、
また明日に。
2010年08月14日
褒めるのはタイミング勝負
…確か、脳科学者の茂木さんだったと思うんですけども…
(本で読んだのは確かなんですが)
褒めるというのは、
タイミング勝負の部分があるというんです。
後からじんわり、承認するというのもいいんですが、
子どもがいいことをしたとき、
頑張ったとき、
「これをやってみて」と伝えて実際やったときなどに、
すかさずそれを褒める、
というのが一番いい、というものでした。
「褒め」に「アスリート」という言葉がくっつくのが不思議だったんですが、
つまりは
「すかさず褒めるためには
子どものことをしっかり見る、観察するということをしなきゃいけない」
ということらしい。
悪いことをしたらすかさず叱る、というのは、
比較的やりやすいんですが
(その行為によって、自分に被害が及ぶ時なんか特に)
いいことをしてすかさず褒める、というのは
意図的に相手を見ておかないと、なかなか難しいのかもしれません。
ベビマのマニュアルを購入してくださった方に
その後のステップメールをお送りしているんですが、
子どもをよく見ていく、
タイミングよく褒めていく、伝えていく練習として、
ベビマを使う方法をお伝えしています。
(だからベビマは一生ものですよ~なんて
言ってたりするんです、私)
話が脱線しましたが、
子どもを褒めることは、
子どもの成長を促すためにも、やっぱり必要だと思います。
だからこそ、
子どものいいところを見つける目を
親自身も身につける必要があるかもしれません。
いいところは、
見方を変えると
いくらでも出てくるものだと思いますよ。
2010年08月14日
【絵日記】このおなかの動きは…!
ええもう、私がイラストを描いていたことなんて
忘れてた&知らない人がほとんどだろうな、というくらい
お久しぶりにかきましたわ。
本来、文章書くほうが得意なんで。
(絵を一本描くのと
あの長文書くのがほとんど同じ時間。
…と言っても15分くらいだけど)
でも、たま~にだとは思いますが、
近況&情報も載せていこうかなと、思ったりしています。
先日行った、地域のお祭り。
そこで見た、ヒップホップの踊りに触発されて、
ムスメが踊りだしたところ、
おなかの中で
小さな動きが…!!!

まだ寝っころがってる時しか感じない程度だし、
外から手をあててもわからない程度だけど、
明らかに、
なんだかものすごく、懐かしい(5年ぶりの)
「自分じゃない生き物の動き」ですよ!?
しかし、その日やっと5ヶ月に入った日。
は、早くないかね?
調べてみたら、
普通、胎動を感じるのは
5ヶ月の後半あたり。
でも二人目の場合は、感じるのが早いことも多いとか。
…なるほど。
おなかの中でシャボン玉がはじけるようなその動きは、
ムスメが踊っているときだけ感じて
踊るのをやめると止まる、という
不思議な体験でした。
よくわかんないけど、
お姉ちゃんが大好きなんだろうということにしておきましょう♪
それ以降、
「赤ちゃんが踊るかもしれないから♪」と
ムスメが舞いまくってます。
2010年08月13日
帰省して、苦しくなっているママさんへ
年末年始に引き続き、
いつもと違う、おじいちゃんおばあちゃんと
一緒にすごすことの多くなる、お盆の時期、
今日は、そんな中
実は凹んでいるママさんのための記事かもしれません。
昔の世代とはまた違う育児を
微笑ましく見てくれる、年配の方ばっかりだったらいいんですが、
話を聞くと、
そうでないパターンというのも、まだまだ結構あるようです。
「子どもを泣かせたら、親が悪い」
「風邪をひかせたら、親が悪い」
「そんなに抱っこばっかりして、抱き癖がつくわよ」
「そんなに甘やかしたら、子どもが付け上がる」
そんな風な、周りの目に
息が詰まりそうになるママさんの相談は
結構あるんです。
というか、
周りが何も言わなくても
「そう思われているんじゃないか」という思いが
私達を縛ってしまうような気がしています。
お盆で、帰省されている方も多いんじゃないでしょうか。
おじいちゃんおばあちゃんが
赤ちゃんをかわいがるばかりに言う、
ちょっとした言葉で
辛い気持ちになってしまうこともあります。
ちょっと泣いちゃったら
「あらあらかわいそう」
ちょっとぐずったら
「暑いんじゃないの?おっぱいが足りてないんじゃないの!?」
頑張っている時ほど、
そういった「ちょっとした」言葉が刺さるんですよね。
相手に悪意があるわけでなくても。
「今は違うんですよ」
「これが正しいと今は言われてるんですよ」
そう言って、わかってもらえたらいいんですが
(私の場合、立場上「専門家だからわかってるはず」と
理解してくれる義母だったから楽でしたが
逆に実の母が聞かない人で(笑)
困ったことも時々ありました…)
そうでないことも多々あるし、
一つ一つ伝えていくのも、結構手間がかかる…。
そういう時は、どうか、
ちょっと目線を変えてください。
あなたを責めているわけじゃなくて、
赤ちゃんを大事にしたいだけかも。
おばあちゃんにしてみたら、
昔と「常識」が違って、
今の常識を認めてしまったら、
自分の育児を否定されるような気持ちになっちゃうのかも。
相手の話も
落ち着いて聞けるのであれば、
それは一安心。
でも、もし
相手の言うことに苦しくなるようなら、
今だけはとりあえず、
自分の育児でいっちゃっていいと思います。
振り回されて、
落ち込んで、
自分なんて駄目だって思うよりは、
ずっといいと思うんですよ~。
今日の提案
時々しか会わない相手の意見、
一理あるな、違う意見も聞いてみようかな、というような
心の余裕がある時はいいのですが、
そうでないのであれば、
どうか、自分の育児を信じてみてください。
悩んだり、
凹んだりすることのほうが、子どもにはよくないかも。
余裕ができたら、
相手の言うことにもちょっと耳を傾ける、
というくらいでいいんです。
ママがニコニコ、幸せ気分でいることが
一番大切だと思いますよ。
こちらの記事も、参考にどうぞ。
周りからの意見は自分で選んでいいんです
育児書どおりには育ちません
2010年08月13日
虐待が注目されてる今だから
(今日書いた記事はこちらです■)
ちょっと一息、
お礼を兼ねた記事です。
ちょっと前に、虐待の話を書きまして、
(こちらの記事です)
いまだに「それいいですね!」メールをいただくことがあります。
(ありがとうございます)
ブログででも紹介してくださる方もいらっしゃいまして、
せっかくなので、
お礼がてら(お礼になるかしら)こちらからも紹介しておこうかと。
maffyさん
「あなたができること。わたしでもできること。 」
皆様、ありがとうございました~。
最近、虐待予防をするためにはどうしたらいいのかと、
そんな話が高まっているような気がします。
どの子どもも幸せにしたい、
これ以上悲しい子どもを増やしたくない、
そんな気持ちが高まっている今だからこそ、
「とにかく通報」
「ダメな母親からは子どもを引き離せ」
ということだけではなく、
(そういう論調もあるんですよね)
そういう状況に陥らないように、
ママさんをフォローできる体制を、
子育てをしている立場だからこそ、作っていけないかと思っています。
虐待などの悲しい結果になる前に、
今、大変ながらも頑張っているママさんに
「頑張ってるよね」とか、
「頑張ろうね」とか、
(「こうしたらいいんだよ」という指示ではなく、
頑張ってることへの励まし、かな)
声をかけてあげるだけでも、違ったりするようです。
(前の記事でもそんな風に書きましたが、
それへの反応メールをなどでも、
「私もそうだった!」という声がかなり多く寄せられました)
もちろん、
そんなのは甘っちょろい(苦笑)と言ってしまいたくなるくらい、
ひどい状況、というのもまた、立場上知ってはいますが、
いろんな段階の人がいますし、
なにより、これくらいなら誰でもやりやすいんじゃないかと思ってるんで、
副作用もないんじゃないかと思います(笑)。
賛同してくださる方がいたら、
頭の片隅でもいいので残していて、
何かあった時に、ちょっと実行する人が増えたら
少~し、育児をするときの「周りの目」が
優しくなってくるんじゃないかと、期待している私です。
2010年08月13日
褒めるのって、どこを見るの?
やっと終わりが見えてきました(笑)
…いや、まだやっと後半、かも。
いつも長くすみません。
今日の記事が、質問された方には一番読みたかったことじゃなかろうかと
思ったりするんだけど
(今頃気付いた)
とりあえず、書いていきます。
(あぁごめんなさい)
子どもを褒める、
承認するというのは、
見方さえ覚えたら、いくらでも出てくると思うんです。
きちんとトイレに行けた、
ちゃんと朝起きてくれた、
小さい頃は、
目が覚めた、立った、歩いた、
そんな簡単なことで褒めるんですが、
そのうちだんだん、親のほうもそんなことには慣れてきちゃって
「そんな当たり前のことで」
と、褒めなくなっちゃうんですよね。
まぁ確かに、
小学生位の子に
「今日も元気に歩いてくれてありがとう」と言ったら
多分怪訝な顔をされますが…。
でも、ここまで極端じゃなくても、
「あなたは起こさなくても朝起きてくれるから助かるわ~」
「トイレに行ってくれるようになったから、
楽になったな~」
前に書いた「承認」のやり方で、
自分の感謝を伝える、という方法で、
伝えていくと、
伝えられると思います。
褒めることは、「ちょっと前との比較」。
完璧に成長した「子ども」との比較だと
できてないところは確かに山ほどあるだろうけど、
その子のちょっと前と比較したら、
できるようになってることって、本当にたくさんあるはず。
数日前、半年前、一年前、数年前、
そんな頃を思い出したら、
今できてることも、できなかったことが
たくさんあるんじゃないでしょうか?
そういうところを「指摘」して、
「あなたはこんなところが成長してきたのね」と伝えることが
褒める=できたところに気付かせる=自信を持たせる
ということになるんじゃないかと思います。
まだ続きますよ~。
2010年08月12日
ちょっと頑張る目標とご褒美を
私にとって、なんだかものすごく思い入れがあったりするんですが、
先日から、その講座(21日間のメールレッスンがあるので)を終了した方へ
順次、『修了証』をお送りしています。
写真を送ってくださった方には、
写真入りのものにしたりして。
前にここでも紹介した
「ありがとう名刺」も同封してみたりして。
(このあたりは私の趣味です・笑)
結構手間がかかったにもかかわらず
(いろいろやってるうちに、いろんなものをやりたくなっちゃって・笑)
写真も撮れなかったな~と思っていたら、
こんな風にブログで紹介してくださった方がいらっしゃいました♪
こちらの記事です。
わーい、ありがとうございます~♪
(ぜひ見てみてくださいませ。
正直、私が撮るより綺麗かも。
感謝です♪)
今回、やりたかったのは、
ただ修了証を渡したかったんじゃなくて、
『その方一人ひとりが頑張った証拠』を何か残したかった、というのもあったりします。
赤ちゃんのために、
ベビーマッサージをやってあげようと思ってくれて、
私を選んでくれて、
実際行動にうつしてくれて、
しかも長い時間をそれに費やしてくれた。
この『まず行動した』というのがとっても大事で、
その一歩目を踏み出すのが、なかなか難しかったりするんですよね。
一歩目を踏み出しさえすれば、
あとは勢いがついて、行動が続いたりするもんなんですけども。
で、そこまで頑張ったぞ、私偉いぞ、と思ってもらえるための証拠になればいいなと
願ったりしています。
子育てをしている中で、
自分自身にご褒美や、一区切りをすることって
少ないような気がします。
自分が学生のころや、
独身時代って、
何かにつけて、自分にご褒美をしていたり、
(それもやりすぎるといけないけどね・笑)
ここまで頑張ったという『区切り』があったりしたんですが、
子育てって、ある意味エンドレス。
こんなに大変で、
こんなに頑張ってるのに、
終わりも区切りもなくて、
ものすごく先が見えないような気持ちになって、
毎日が長い長いトンネルに入っちゃったような気がして
滅入っちゃったりする人も多いように思っています。
だから、
自分で、どこかに『区切り』を作って欲しいんです。
誰かが(特に旦那様とか?)
どこかで「お疲れさん、これからもよろしく」
と言ってくれればいいんですけども、
なかなか相手も忙しかったりして、
そうもいかなかったりするので、
自分で、管理することが必要かも。
ちょっと疲れたときや
誘惑に負けた時に手に入れた「何か」より、
自分が「これを頑張ってきたぞ」という
証拠になるご褒美というのは、
とっても大切な、頑張る活力になると思います。
ぜひ、ご自分でも試してみてくださいね。
今日の提案
小さな目標、小さな頑張ることを作ってみませんか?
そして、それが終了、達成したら、
自分にご褒美、してみましょう。
そのご褒美は、長い時間あなたに自信を与えてくれる
大切なものになるかもしれませんよ。
文中のベビママニュアルはこちらで紹介しています。

赤ちゃんともっとふれあいたくなるABC
マニュアルへの修了証、
現在順次お送りしていますので、
まだ届いてない方はちょっとお待ちくださいませ~♪
2010年08月12日
でもやっぱり認めないとね
「褒めるのが苦手な人なら、
少しだけ褒めるのはどうだろう」ということで
書いてみました。
今度の記事は、
それをさらにひっくり返して、
「でもやっぱり褒めたほうがいいよね」という話。
(「どっちなんだ!」と突込みが来るかしら…・笑
好きなほうを取って欲しい、というか、
しっくり来る方が、あなたにとっては正しい、というのは
このブログを読んでる方ならわかってもらえると信じて)
この記事では、
「褒め」と「承認」を一緒にしています。
前にも書いたように
厳密に言うと違ったりするんですが、
肯定的に言われて、相手が嬉しくなるということについての
お話です。
相手について、褒めるのが苦手な人もいますし、
そんなに子どもを褒めたら調子に乗る、
という人もいると思います。
でも、子どもはやっぱり、
自分の存在を認めてもらうことを求めていると思うんです。
いきなり高いレベルのものを求めて、
そこにたどり着くまでは褒めない、というんではなく、
小さなこと、できたことを少しずつ褒めたほうが
やる気が出ることも多いですし、
何より自己重要感が育っていくと思います。
特に小さければ小さいほど、
「自分は素敵なんだ」
「頑張ればできるんだ」
という自己重要感を育てることが必要だ、
というのが私の持論です。
自分なんて駄目かもしれない、
生きていても仕方がないかもしれない、
そういう意識は
大人になってもずっと自分をさいなみ続けます。
逆に
自分はできる、と思えるかどうかというのは
親がきちんと自分を見ていてくれた、
自分はこんなことができた
(小さな成功体験の記憶)
なんかよくわかんないけど、自分はすごいらしい
(根拠はないけど自分を信じられる自信)
という思いがあってこそ、ではないでしょうか。
小さい子どもにとって親というのは絶対な部分がありますから、
親が「すごいね」といえば、すごいことなんだと理解するし、
ひたすらけなされて怒られて成長すれば、
(その場では行動を変えるかもしれないけれど)
「自分は悪い子なんだ」という前提が先に出てしまう、かも。
ひどい大量殺人などの裁判で、
小さい頃の育児環境が劣悪な人って
結構いますよね。
それで許されることではないだろうけど、
「もしこの人が、自己重要感をしっかり育てられてたら
どうなってたんだろう」
と思うことはたくさんあります。
だからそれぞれのパパママが
子どもが認められたと「感じられるように」
伝えて欲しいなと思ったりしています。
(「感じられるように」というのは
ただおだてのように褒めても、褒められたと感じられなかったり、
伝わってなかったりすることがあるからです。
やっぱり基本は、「きちんと承認できたかどうか」
ということになると思うので)
褒め方の記事、そろそろ最後になるので、
じゃあどこを褒めるの?という話、
書いてみようと思います。
2010年08月11日
子どもをがっつり叱った後で
先ほどムスメとバトりまして(笑)
今日は主にムスメの精神的フォローのため
夜をべったりタイムにしますので、
今日のハッピーママ、お休みします。
すみません~。
(お昼のうちに、書いておけばよかった…)
叱った後って、大事だと思ってまして。
叱って、
思いっきり泣いてもらって
すっきりした後が一番「入る」感じ。
少なくともうちのムスメに対しては…。
見に来てくださった方、すみません。
ムスメと一緒にこの後語って、
起き出せたらまた書きたいんですが、
ちょっと、自信なしです。
(一緒に寝てしまう可能性大)
え、えと、
また明日に~。(先に謝っておくらしい)
2010年08月11日
「褒める」のが苦手な人は?
私のように、軽い気持ちで(笑)褒め褒めができる人もいるんですけど、
どうも
そんな軽く褒めるのは難しい、という人もいますよね。
(そういう人は、自分にも厳しかったり、
向上心が強くあったり、
どんどん物事を正しく改善していくイメージがあるけど
どうなんでしょう)
今日は、そんな人へのお話。
どうしても軽く褒めるのが難しい、
という場合には、
あえて「褒めよう」と思わなくても
いいんじゃないかと思ってます。
それは、
前の記事でも書いたように
「承認」という事実を伝える方法を使って
相手に肯定感を与えればいいんじゃないかと思うし、
普段褒めない人だからこそ、
重い「承認」ができるんじゃないか、ということも
あるからです。
普段、全然褒めてくれない上司が
ぽつりと
「いいものができたな…」と評価してくれた。
なんだか、ものすごく
ずっしりとくる感じがします。
昔の「親父」って
こんな感じだったのかもな、と思ったり。
どうも自分には、褒め褒めは違和感がある、という場合には
お試しくださいませ。
2010年08月11日
今日はメルマガの配信日です
近くを通った(らしい)ここ鹿児島は
少なくとも私の家は
全くと言っていいほど、影響がなかったんですけども、
(台風?いつきた?)
皆さんのところはいかがでしょうか?
台風といえば、いきなり天気が変わったりしますので、
どうぞ気をつけてくださいね。
さてさて今日は、メルマガの日です。
早速クイズ、いってみます。
●○●○─────────────────────○●○●
| 夏は中耳炎が気になる季節。
| 夏休み、大丈夫でしょうか。
| 私は夏になると必ず中耳炎になるタイプだったんです…
| 中耳炎に悩む子は、結構いるみたいですね。
| 中耳炎になったときの対処法、復習してみませんか。
●○●○─────────────────────○●○●
痛いんですよね、中耳炎…。
大人になったらならなくなったものの、
小さい頃は、本当に毎年中耳炎になってまして、
ムスメも中耳炎になりやすいタイプみたいなんで、
夜に「耳が痛い」と泣かれるのが恐怖です。
(なぜかいつも、夜なんですよね)
ということで、今日は
中耳炎の対処法いきますよ。
覚えておくとちょっと楽かも。
よろしければ、
ぜひ読んでくださいね。
メルマガは、今日の9時ごろ(?)
配信予定です。
メルマガ、まだ登録されてない方は、
よろしければ

こちらのメルマガ登録か、
右上のバナーからどうぞ。
(携帯の方は、リンク先に飛んだあと、
「ハッピーママになる方法」で
検索してくださいね)
2010年08月10日
新月パワーで願いをかなえる!
新月の日って、
願い事をするとかないやすい、と言われる日。
私も(忘れなければ)新月のときは
自分の望みを再確認するために
書くようにしています。
何か願い事がある時はわかりやすいんですけども、
実際、
「あなたはどんな自分でありたいですか?」
「どんなことがかなったら嬉しいですか?」と聞かれると
結構答えられないもんなんですよね。
でも、私が知る限り、
どんどん夢をかなえていったり、
どんどんいいことが起こったりしている人っていうのは、
みんな夢を明確にするのがうまい、気がします。
夢を語る、という場合でも、
なんかものすごく明確で、鮮明で、
夢を語ってるはずなのに、
もうすでにかなってるとか、
数ヵ月後にかなうというか、
今後当然起こる、「計画」にしか聞こえなかったり。
このあたりが「夢を夢で終わらせない」秘訣なのかなと
思ったりします。
新月っていうのは、
だいたい毎月やってきますから、
そのときに自分の目標とか夢を
確認したり、考えてみたりするのもいいかもしれませんね。
私も早速、書いてみましたよ。
今回、今まであんまりなかったような「こうなったらいいな」が
降ってきた(笑)ので、
それも書いてみました。
「学ぶことと伝えることが仕事になって
毎日を楽しく充実させています」
うん。かなったら面白い。
少しずつ動いてみようと思います。
新月のパワーは二日ほど続くらしいので、
明日でも大丈夫みたいですよ。
ぜひぜひあなたの望み、書いてみてくださいね。
今日の提案
あなたの夢、紙に書いてみませんか?
お月様のパワーを借りる、とかいうと、
なんだか力が出そうな気がしたり。
こうやって「書く」ことは、
自分の望みを探るためにもいいかもしれませんよ。
2010年08月10日
褒められ方にもタイプがあるらしい
「私の場合はとにかく褒める意志を感じたらそれだけで嬉しい」
というようなこと書いたんですけども、
実はここに、ちょっとしたポイントがあったりするようです。
人にはい
ろんなタイプがあって、
物事の受け止め方が違うんですよね。
ただただ、おだてでもいいから褒められたりとか、
自分の方に関心を向けてくれてたりだとか、
それだけでうれしい人もいるし、
逆に
むやみやたらに褒められたら
「何もおだててるんだ」
「何の下心があるんだ」
というように感じる人もいる。
(自分にない感覚だったんで、
始めて知ったときには驚きました)
そういや、子どもでも
いきなり「あなたはいい子ね~」と言われたら、
「何かある。手伝いでもさせようとしてるのか!?」と
警戒したりしますしね(笑)
そういう
「ただ褒められるだけじゃ駄目」
というタイプの人にも
「承認」は使えますよ。
だって、事実ですから。
事実だったら、否定のしようがないですものね。
(私の主人も、
何か褒めると「いや、そんなことはない」「たいしたことないし」
と全て謙遜されてしまうんで、
事実を伝えないと伝わらない…)
ただ、承認するためには、
しっかり相手を「見る」ことが必要になります。
「おべっか」や「おだて」では
見抜かれてしまうんです。
そういう意味では、
素直に乗せられてくれるタイプの方が楽といえば楽ですが(笑)。
あなたのお子さん、
そして褒めてあげたい相手のタイプも
よく見てみてくださいね。
2010年08月10日
「褒め」と「承認」の違い
「褒め」と「承認」は違います
というようなことを書きました。
あの記事で、何が違うのか、
わかりましたでしょうか?
「褒め」というのは、
ある意味、褒める側の主観が入った
「評価」になってしまうことがあるんです。
「トイレができてすごいね」
(できなかったらダメなの?)
「100点とって偉いね」
(100点じゃなきゃ、意味ないの?)
これに対して、「承認」は
褒める側の主観ではなく、
本人がやった「事実」そのものを指摘することにあります。
「トイレを教えてくれたんだね」
「100点取れるくらい頑張ったんだね」
できてる所を伝えて、
あなたはすごいんだね、ちゃんと見ているよ、
と伝えることです。
「褒め」は上下関係
「承認」は同じ目線の高さ、
といえばいいのかな。
そして、できるなら
「(あなたがそうしてくれて)ママ助かったよ。ありがとう。」
「嬉しくなるよ」と伝えると、
より一層、相手は喜ぶように思います。
「褒め」と「承認」の違い、
逆に自分が子どもから言われたらどう思うかを考えると
ちょっとわかりやすいかもしれません。
「ママ、いつも美味しいお料理作ってくれてありがとう(承認)」
と言われると、ものすごく嬉しいですが
「この料理、しっかり作って偉いね(褒め・評価)」
と子どもに言われたら
ほほえましく思いつつ、
なんか上から目線でもにょっとした気持ちになる人もいるんじゃないかと。
(私の場合、単純に褒める意志を感じられたらそれだけで、
言葉の内容や相手にも関係なく嬉しいですけども)
そういうもんじゃないかと思います。
なんだか、褒めることに違和感があって、
褒められない、というような方、
ぜひ「承認」を頭においてみてください。
承認なら事実そのものですし、
やりやすかったりするかもしれないですよ。
2010年08月09日
いろんなものは繋がっている
主人のご両親も一緒に外に食べに出かけたんですが、
そこで出てきたお肉が
メニューとかなり違って少なくて、
家族一同、(内輪で)ものすごくつっこんでたんですが、
「口蹄疫の影響ってのはこういうことか」と
なんだか納得しました。
口蹄疫が出始めた頃から言われていたことですが、
宮崎の牛は、全国のブランド牛の元になっているから、
ブランド牛・豚が高騰する
↓
ブランド牛でなくても、和牛・国産豚も一緒に高騰する
↓
一緒に輸入されている牛・豚も高騰する
↓
家計や外食産業直撃
↓
外食では、肉の大きさが小さくなったり
質が悪くなったりする
というような流れがあるそうで。
すでにあちこちで
「肉の量が減った!」という話を聞いてはいたんですが、
まさにこのことか!と
実感した思いです。
(まぁ実際、今はあんまり肉をたくさん食べたくないので、
私にとってはちょうどいいといえばちょうど良かったんですけど)
いろんなものがつながっている、というのは
実はかなりいろんなもので、あるのかもしれません。
例えば、
車でちょっと、道を譲ってもらって嬉しくなった
↓
嬉しいから他の人に何か優しくしたくなって
笑顔で仕事をしてみた
↓
それを見て嬉しくなった人がまた嬉しくなって、
他の人に優しくしてみた
↓
「嬉しい」の連鎖が回りまわって、
自分に戻ってきた
なんてことも十分ありえるし、
逆に
旦那様と仕事に行く前に喧嘩をした
↓
イライラするから仕事にも身が入らないし、
ちょっとしたことで部下にあたってしまった
↓
部下も怒られるかもしれないとびくびくして、
仕事に集中できない
↓
業績伸びず
なんて負の連鎖もありえるかも。
「風が吹けば桶屋が儲かる」法則では、
悪いこと(と思ったこと)がめぐりめぐって
いい結果になることも、十分ありえるけれど、
ほんのちょっとの「嬉しい」を人に伝えたほうが、
いいことが起こっていく可能性は高いんじゃないかと
思う私です。
ちょっと小さな「嬉しい」を
連鎖させてみませんか?
今日の提案
何か嬉しいことがあったら
自分のところで止めないで、
他の人に「嬉しい」を伝えてみませんか?
余裕があったら
自分から「嬉しいこと」を発信してみませんか?
めぐりめぐって、
大きな幸せができあがるかもしれないと、
そう思っています。